医療事務の離職率は高いです。
これは長年医事課に携わってきてほんと実感しています。
そして抜けた人の穴を埋めるために新規に事務員を採用するのですが、これがなかなか定着しません。
それもかなり短期でやめていく人がたくさんいます。
なぜ、ここまで定着しないのか?
どこに問題点があるのか?
今回はここの所を深堀りします。
同じような悩みを持っている人はぜひお読みください。
なぜ思うように新人が育たないのか?
その理由がきっと見えてくるはずです。
目次
新人教育って何が正解?【医療事務の新人教育論】
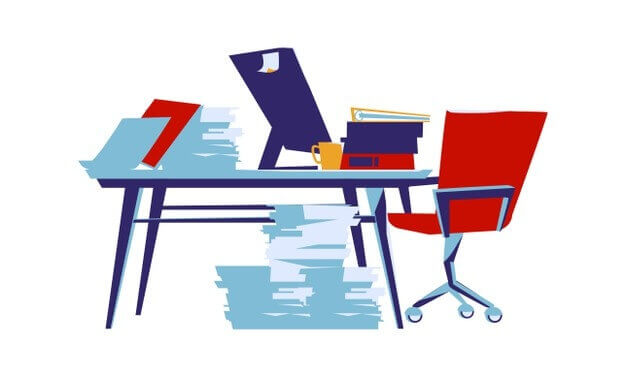
結論
教える側の資質が問われています。
医療事務の新人教育論
実務経験者なんて来ない
医療事務において新人とは4月に新入職者として入って来る場合もありますが、ほとんどが中途採用です。
それも期間に余裕を持たせて退職する人が少ないため、急な求人募集、面接、採用合否と非常にスケジュールがタイトです。
それにより本来なら実務経験者がほしいのですが、はっきり言って履歴書で選り好みしている余裕はありません。
そもそも実務経験者が応募してくること自体少ないのが現状です。
それに実務経験があるといっても、外来受付、料金計算、外来レセプト、入院係、病棟クラーク、医師事務作業補助、診療情報管理等、どの職種なのかで全然違ってきます。
最近の当院の例でいきますと、入院係の欠員が出たため募集したのですが、入院係の実務経験者が応募してくることはまずないです。
となると外来受付、外来レセプトなどの経験者であってももう実務経験という点ではないに等しいです。
まだまったくの素人よりはかじっているだけましという見方もできますが、僕はそうは思いません。
入院レセプトが見れる人は外来レセプトも見れるとは思いますが、逆は難しいです。
外来レセプト経験者でもDPCはゼロから勉強しないといけません。
また、中途半端に経験がある人は自分なりの思考、やり方にこだわってしまう部分があって逆に仕事への慣れ、吸収という点では悪く作用する場合もあります。
なので僕は完全一致の職種を経験していなければ、実務経験有りとはみなしていません。
結局実務経験者なんてほとんど来ない、ということです。
新人教育の2つの問題点
そういう点では入職者の9割は実務経験なしで入ってきます。
そして彼ら彼女達を育てないことには業務は回りません。
そこで新人の教育問題にぶち当たります。
僕はここで2点問題があると考えています。
まず1点は教わる側の問題、そしてもう1点は教える側の問題です。
教わる側の問題
まずは教わる側の問題についてです。
なにわともあれやる気が最重要です。
こんなの当たり前ですよね。
しかし、そこさえもあるのどうかあやしい人もいます。
また、おとなし目の人も損な傾向があります。
医療事務ってやることが非常に多くあります。
ですので覚えることが次から次へと、どんどん出てきます。
そのため、受け身では間違いなく仕事はできません。
手が空いたら次は何をすればいいか、どんどん聞くぐらいじゃないとまず無理です。
今忙しそうで聞けないかなって思う必要はなく、むしろ不躾なぐらいがちょうどいい。
というかそれぐらいのパワーがないとやっていけません。
また、教わったことをメモするのは言わずもがなですが、復習が大事です。
人は1日経ったら約7割忘れます。
その日は覚えていても2、3日後同じ処理案件が出てきた場合復習していなければ、同じ事をまた聞かないといけなくなります。
そこでまたそのままにしておくと、1週間後その処理案件が出てくればまた聞かないとわかりません。
ここまで来ると教えている側は覚える気あるのかな?やる気あるの?って感じます。
そして「この新人はできない人」という判断を下すのです。
医療事務に必要な能力って何?
話は変わりますが、医療事務に必要な能力って一体何なのでしょうか。
まったく経験なしで入ってきた人で「思っている仕事とは違った」と辞めていく場合がありますが、どういうイメージをされているのでしょう。
デスクワークでひたすら書類を処理し、キーボードを叩いてとかなんでしょうか?
実際はもっと煩雑です。
担当の仕事をこなしつつ患者対応もしつつ、医師からの質問に答え、おまけに電話が鳴る、みたいなマルチタスク的な業務のやり方はよくあることです。
1つの事だけ黙々と行うなんて業務はまずありません 。(一部診療情報管理の業務などは比較的そちらに近いですが)
医療事務の仕事においては知識的な能力ももちろん必要ですが、自発的にどれだけ動けるか、臨機応変な対応力の方がより重要です。
それこそが医療事務に必要な能力なのです。
教える側の問題
次に教える側の問題について見ていきます。
簡単にいえば教え方についてです。
これには2つ方法があります。
ビシビシ厳しく教えていく方法と、ひとつひとつ丁寧に教える方法です。
これはもう結論が出ていて、ビシビシ厳しくはもう時代にそぐわないです。
僕の新人時代は、厳しく教えるが常識でした。
「自分で覚えなきゃ誰も教えてくれないよ」「解釈読んどいてね」「前言ったよ」等理不尽だなって思ったこともありましたが、逆にそれをバネに頑張れたのでそれはそれで良かったです。
ですが、今の新人の人達にそれをやると確実に辞めていきます。
それでは人材は育ちません。
大事なのは育てるという意識です。
しかし、実際は厳しく指導する教育係の方が多いです。
これは特に女性に多いように思いますが、「自分の時は何も教えてもらってなかった」「すごく厳しく指導された」「私の時はこうだった」として自分が受けた仕打ちは同じように与えなければ不公平だ 、みたいなすごく低レベルな理由で丁寧に教えない人がいます。
このような人はもう自分しか見えていない人なので、育てるという意識はありません。
これはそのような人に教育係を任せた上司の責任です。
ですので新人教育論というのは、いかに教育できる人材を育てておくかという教育係教育論とも言えます。
まとめ

この先医療事務の仕事は、ICT化によって人材が淘汰されていきます。
その中でいかに使える人材を育てていくかが、これからの課題です。
その観点からすると、新人教育はとても重要な部分です。
つまりどう教育、指導していくかという現場の資質が問われているということです。
辞める人がいる場合本人の問題だけではなく、この現場の資質がもたらす影響が軽視できません。
新人の彼ら彼女達をどう育てていくか、問われているのは我々の能力です。
新人教育に決まった答えなどありません。
彼ら彼女達と同様僕たちも、試行錯誤を繰り返しながら成長していかなくては未来はありません。
もう一度自分が新人だった頃の気持ちを思い出した上で、どういう教え方がベストなのかを探っていく作業が必要です。
「こいつできねえな」と新人にレッテルを貼ることは簡単です。
でもそれでは何も解決しない。
本当にできないのは、きちんと教えられないあなたかもしれません。
【関連記事】
 新人教育には何が必要?【新人教育のコツとは】その①
新人教育には何が必要?【新人教育のコツとは】その① 新人教育には何が必要?【新人教育のコツとは】その②
新人教育には何が必要?【新人教育のコツとは】その② 新人教育には何が必要?【新人教育のコツとは】その③
新人教育には何が必要?【新人教育のコツとは】その③ 新人教育には何が必要?【新人教育のコツとは】その④
新人教育には何が必要?【新人教育のコツとは】その④


