以前の記事で有能、無能という話をしました。
 有能と無能と無力【医療事務仕事論】
有能と無能と無力【医療事務仕事論】
その中でいろいろ持論を述べましたがそもそも有能、無能の判定はその評価者によって大きく変わってくるので一概に区別することはできません。
そうはいっても組織においては「あの人優秀」「あの人無能」という判定はだいたいできあがっていて、個人の見方に若干のズレはあっても有能と見なされている人はだいたいの人から有能と判定されていますし、無能と思われている人はだいたいの人からそう思われています。
以前のその記事では仕事上では無能ということはなくてそれは無力ということではないか?と書いたのですが大部分の人の認識は「無能な人=無力な人」だと思うのでそこは言葉のあやの問題でそんなにこだわる必要もないのかなとも思います。
ですので今回は無力というのは省きましてシンプルに有能、無能ということで話を進めて行きます。
前置きが長くなりましたが今回のテーマは「組織って無能の集まりですか?」ということです。
ここにフォーカスしていきます。
 ごまお
ごまお
目次
【有能な人はいなくなる?】組織って無能の集まりなの?【ピーターの法則】

結論
全体のシステムとしてどう機能させるかが大切です。
組織に有能な人はいなくなり、無能の集団と化すということの理由には2つあります。
1つはピーターの法則であり、もう1つはできる人は辞めるからです。
ピーターの法則
ピーターの法則
1.能力主義の階層社会では、人間は能力の極限まで出世する。
したがって、有能な平(ひら)構成員は、無能な中間管理職になる。
2.時が経つにつれて、人間はみな出世していく。
無能な平構成員は、そのまま平構成員の地位に落ち着く。
また、有能な平構成員は無能な中間管理職の地位に落ち着く。
その結果、各階層は、無能な人間で埋め尽くされる。
3.その組織の仕事は、まだ出世の余地のある人間によって遂行される。
ウィキペディア 引用
これはつまり「役職や階級のある組織では各階層メンバー全員がいずれは無能で埋め尽くされることになる」という法則です。
たとえば平医事課員・主任・係長という階層に分かれているとします。
この場合、無能な平医事課員はいつまでたっても平医事課員のままで階層が固定され、有能な平医事課員は主任に昇進します。
その結果平医事課員の階層には無能な平医事課員ばかりが残ることになり、いずれは平医事課員の中に有能な平医事課員は1人もいなくなります。
そして主任でも同様のことが起こり、無能な主任はいつまでも主任でい続け有能な主任は係長に昇進してしまいます。
その結果主任クラスから有能な人材だけがどんどん抜けていき後に残ったのは無能な主任ばかりになってしまいます。
この現象は各階層で同じように起こるため最終的には各階層の全員が無能な人たちであふれかえるというものです。
つまり有能な人はどんどん上の階層に上がっていくのでその階層にはいなくなるということです。
これでいくと医事課長でずっとい続けている上司ならば無能な医事課長になりさがっているというわけです。
そもそも優秀な医事課長ならば医事課長じゃなくて医事部長になるはずだという論理です。
そう聞くとなるほどなと思える法則です。
ですがそれでいくと無能の集まりで組織が成り立つの?って思うのですがピーターの法則にはその答えが3つ目に示されています。
すなわち
3.その組織の仕事は、まだ出世の余地のある人間によって遂行される。
ということです。
つまり「現在の役職から昇進する一歩手前の段階にいる一部の有能な人材だけが成果を作っている」ということです。
これはいわゆる80:20の法則(パレートの法則)の考え方と近いです。
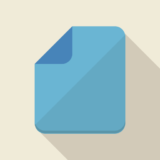 「働きアリの法則」は人間社会の組織には当てはまりません【これはウソ!】
「働きアリの法則」は人間社会の組織には当てはまりません【これはウソ!】
80:20の法則とは「成果の8割は全職員のうちの2割で生み出している」という法則です。
現在の役職から昇進する一歩手前の段階にいる一部の有能な人材がおおよそ2割ぐらいいると考えるならば、ピーターの法則とパレートの法則の言いたいことはほぼ一致していることになります。
そしてこれをまとめると組織は一部の有能な人と大多数の無能な人で成り立っているということになります。
 ごまお
ごまお
できる人は辞める
仕事ができる人ほど辞めていくというのはよく聞く話です。
だったらそれはなぜなのか?
答えは仕事ができるからです。
これだと意味が分かりませんからもう少しかみ砕いて説明します。
私が思う仕事ができる人というのはメタ認知力が高い人です。
そのような人は常にずっと先を見すえています。
だからこそひとつの職場はあくまで通過点なだけであり踏み台にすぎません。
そして食いぶちを稼ぐために働いている程度の意識の人とは全く違う次元、ステージにいます。
ですので必要とあらば転職もいとわないキャリアアップ思考の高い人です。
だから今の職場で正当な評価がされなかったり、もう学べることがないと感じたらすぐに見切りをつけることができるのです。
つまりできる人ほど積極的に挑戦していくし成長志向なのでどんどん辞めていってしまうということです。
反対に仕事ができない人ほど変化を嫌うし、さらなる努力なんかしたくないので現状の職にしがみつくことになるのです。
結果として有能は人はどんどん抜けていき、残るのは自己成長しようとしない無能な人たちばかりとなるわけです。
結局最後までい続けるのは文句は言うが自分では動かないという無能な批評家の人たちばかりです。
そしてそのような人が増えれば増えるほど有能な人はアホらしく思い嫌気がさして余計に辞めやすくなります。
まさしく負のスパイラルなのです。
 ごまお
ごまお
組織はなぜ回るのか?
上記の2つから導きだされる結論は組織は無能で染まる、ということです。
ですがこれだと組織が無能となってしまいます。
でも実際にはきちんと回っているとすればいったいどういうことなのか。
1つは上述したような80:20の法則も働いているのでしょう。
ですがもっと大事な要素がほかにあります。
それは組織は組織なんだということです。
トートロジーですが結局言いたいことは組織というのは個人の能力に依存してはいけないということです。
優秀な組織というのは個人の優劣が組織の優劣に影響しない組織だということです。
まとめ

ピーターの法則でいくと組織は無能な人で埋め尽くされてしまいます。
しかし上記で述べたとおりたとえ無能な人が増えたとしても組織はそこに影響を受けてはダメなのです。
優秀な組織というのは個人の能力に依存することはないのです。
全体のシステムとして上手く回せている組織が有能な組織でありそこに構成する人の能力なんて関係ないのです。
ですので極論すれば無能な人だけになったとしてもシステムとして上手く回っていればそこは有能組織なのです。
ですが実際それはなかなか難しいです。
現実的で実体に近いのはやはり80:20の法則の方かなとは思います。
2割ほどの一部の有能な人が全体の8割の成果を上げている。
ここまでは極端だとしても一部の人だけに仕事が集中し偏った生産性で回っている組織は結構あると思います。
これは良しとするのかしないのかという話ではないです。
もうそういうものなんだということです。
だからこそ法則化されているのでしょう。
要は使い方の問題です。
個々の能力をどこで活かせられるか、適材適所な配置ができるかということです。
以前の話で述べたとおり無能な人というのはその状況、場面において無力な人のことです。
それは全て相対的なものです。
極論すれば人間として絶対的に無能な人なんていません。
有能とされる人はたまたまその職場環境にマッチしていて優秀と評価されることによってどんどん仕事が集中しそしてそこに生産性が集中する。
逆に無能と評価される人は担当している業務がたまたまマッチしておらず上手くできないことが余計にまわりの確証バイアスを招きますます評価が落ちていく。
そういうことが実際起こっているのだと思います。
組織として考えるべきはその格差を助長してはいけないということです。
組織が上手く回るというのは全体のシステムが上手く機能している状態です。
そのためにはなるべく偏った生産性をフラットな状態に近づけないといけません。
できる人が2人、普通が6人、できない人が2人の組織ではそのできる人2人が抜けたとき生産性は急激に落ちるわけです。
そしてできる人は辞めていくのでそこに依存している組織は危ういのです。
すべきことは普通の人6人のレベルを底上げしていくことです。
そうすることでできる人がいようがいまいが影響を受けない組織が構成できます。
あとできない人2人を普通グループに近づけるような業務配置を考慮することです。
つまりエースで4番を育成するのではなくてきっちりと仕事をする2番打者を何人もそろえておくことの方が大事だということです。
結局有能な人がいなくても全体のシステムとしてきっちりと結果がだせる組織が有能な組織なのでしょう。
個人に依存しない組織づくりを心がけ肝に銘じたいと思います。
 ごまお
ごまお


