以前に仕事論としていくつか記事にしました。
 挫折なしで成長なんかできない【倒れても起き上がればいい】
挫折なしで成長なんかできない【倒れても起き上がればいい】 医療事務のプライドを捨てると仕事はきっと上手くいく
医療事務のプライドを捨てると仕事はきっと上手くいく
私の医療事務仕事論におけるスタンスは「挑戦して失敗しよう」「臆せず変化に飛び込んでいこう」というものです。
これにはそれなりのモチベーションが必要になります。
自分なりの目標がないとそういう思考にはなりません。
そして最近特に思うのは私のような考えはかなりのマイノリティだということです。
今回は医療事務とモチベーションについて述べていきます。
目次
モチベーションの高い医療事務員は絶滅危惧種?【仕事とモチベ】

結論
絶滅危惧種かも。
でも別にいいんじゃね。
医療事務のモチベは高くない
これははっきりしています。
なぜか?理由は次の3つです。
1.給料が低い
2.ヒエラルキーが低い
3.クリエィティブ性が低い
1.給料が低い
これは周知のとおりです。
ですが病院の大小、医療事務職か総合職かなどで給料にはかなりひらきがあります。
また高卒、専門卒か大卒かでも差があります。
単純に中小より大病院の方が高い、事務職より総合職の方が高いです。
ですが総合的にみて医療事務の給料は一般企業と比べてかなり低いと言わざるをえません。
ですが仕事はお金のためだけにしているのではありません。
以前にはそういうことも書きました。
 仕事って結局お金の為?【医療事務の本音】
仕事って結局お金の為?【医療事務の本音】
その記事で言っていることは本心ですがきれいごとと言われればそうかもしれません。
結局仕事は自分の内面の成長のためであってお金は副次的なものなんだと力説したところで自己成長で飯は食えないわけです。
食うために働いているというのも事実なのでその給料が低いというのは死活問題です。
これは男女差別しているわけでなく現実にある一般的なことですが男性の方が死活問題具合が大きいです。
もう今のご時世男性が働いて一家を養うという考えが時代遅れですが、現実にはやはり女性は子供を産む、育てるということに手をとられるわけで、その分男性が働いてお金を稼ぐということはまだまだ一般的です。
その場合夫の職業が医療事務で役職もついていないとなるとかなり厳しいのが現実です。
以前にも書きましたが定期昇給があるとしてもそもそもの基本給が低いのでそんなものは微々たるものです。
だったらあとは資格手当や役職手当をつける以外に給料を上げる方法はありません。
目先のお金を稼ぎにいくのならば当直に入りまくるという荒技もありますが、それだと将来的な展望は何にもないわけです。
また残業代で稼ぐというのも働き方改革が推進されている現状をみれば今後は難しくなります。
ですが当直代や残業代で稼ぎたくなる気持ちも分かります。
私も若い頃はそういう考えに傾いていたときもたしかにありました。
誰だって少しでも多くお金はほしいものです。
そして残業代や手当がない場合、ホントに医療事務で食っていけるのかという手取りになるのです。
そんなことを言ったって自分で選んだ職種なんだから文句を言うのがお門違い、って言われればそのとおりです。
入職時に給料の額は分かっています。
また思い描いていたのと違いすぎて耐えられないというのならば転職すればいい話です。
でもほとんどの人は転職もせずひとところで長く勤めています。
これは自分なりの妥協点、納得点を作っているからです。
それは「給料は低いけど安定している」「一度覚えたらそれだけで末永く職にありつける」ということです。
つまりは「病院はつぶれない。給料は安定している。覚えてしまえば仕事は楽」だからこのままでいいという考えです。
これは給料が低いと文句を言っている人よりもタチが悪いです。
なぜなら特に給料が上がらなくても別にいいという考えだからです。
そして察しのとおりこの人たちに高いモチベーションなんてものはありません。
医療事務は単に生活費を稼ぐための道具にすぎないのですから。
そんな人に自己成長がうんねんかんねんと言ったところで「この人何言ってんの」となるのがオチです。
2.ヒエラルキーが低い
これについても記事にしています。
 病院内ヒエラルキーと医療事務【医事課の役割とポジション】
病院内ヒエラルキーと医療事務【医事課の役割とポジション】
病院はひとつの村です。
村社会ならそこにヒエラルキーあるのは必然とも言えます。
そして医事課の立場から言いますともうそれについては諦めているというのが正直なところです。
「諦めてはダメ。改革の意識を高くもつべき」「病院の上層部はもっと真剣にとらえるべき」という意見も中にはありますが、それこそきれいごとです。
院内ヒエラルキーを変えることなんてほぼ不可能です。
そしてそのことについて考えることほど無意味なことはありません。
でも私はそれでいいと思っています。
そもそもヒエラルキーに乗っかってマウントをとってくる人は大した人ではない、と知ることです。
医事課は事務として正当な意見、要望を投げればいいし、それをどう受け取るかなんて相手しだいです。
そんなことを考える必要はない。
どの職種ともどの部署とも対等だと自分で思っておけばいいだけのことです。
ですが医事課のヒエラルキーが低いことに腹を立てたり、やる気をなくしたりする人もいます。
そしてこのことによってモチベーションは当然下がるわけです。
3.クリエィティブ性が低い
医療事務の給料が低い原因のひとつは医療事務員自体が何かを生み出しているわけではないからという理由をよく目にします。
たしかに医療事務という職種は自発的に何かを生み出しそれを利益に変えているわけではありません。
ですがこの理由はそれこそ前述のヒエラルキーに乗っかったマウントをとった言い分です。
これは単純に医療事務への悪口です。
「君たちは受け身の職種。要はただの事務屋なんだ」と。
ですが医療事務の給料が低い理由はもっと単純です。
それは誰にでもできる仕事と見られているからです。
「いや誰にでもはできねえよ」という意見は無視します。
ここでポイントなのはそう見られているということ自体です。
誰にでもできる仕事の賃金が買い叩かれるのは市場原理から見て当たり前です。
誰にでもできない仕事だからこそそれ相応の対価が支払われるのです。
そして語弊のある言い方ですが今の医療事務の一般的な業務内容から見るとそれなりの対価を支払おうとはなりません。
その場合においては受け身の事務作業という見られ方をしているということです。
そして作業と仕事は違います。
一番の違いは作業にはクリエィティブ性がないということ。
そしてクリエィティブ性のない作業からは高いモチベーションは生まれないということです。
ただ単にやらされている事務作業からいかに病院収益に寄与できるか、患者サービスに貢献できるかという問題解決へ思考をめぐらしシフトしてはじめて仕事となります。
そして仕事からは高いモチベーションは生まれ得ます。
医療事務の特殊性
医療事務のモチベーションが高くない理由は上記に述べたとおりですが、そのほかに医療事務の職場の特殊性も関係しています。
一般企業との一番の違いはほぼ女性の職場ということです。
その比率は通常9:1か8:2。
圧倒的に女性が多いです。
そしてこの場合のデメリットがモチベーションと大きく関係しています。
それは上を目指す人がほぼいないということです。
中にはごくわずかですが出世欲がある人もいますが、ほとんどがそんなことはのぞんでいません。
のぞんでいるのは安定、現状維持です。
逆に外側からの変化は猛烈に拒絶します。
たとえ何らかの役職につけるとしてもそれに関わる責任など一切負いたくないからそれも全力で拒否です。
求めているのは変化しない仕事と自分の環境。
変わらない毎日が続くことで良しとします。
これがごく一部ならばまだ分かるのですがかなりの割合を占めます。
そしてその状況下で「生産性を上げよう」「もっと良くできるように変えていこう」「効率性を高めよう」と言っても響かないわけです。
「私は今のままでいいと思っている。もっと効率的に?自己成長のため?生産性?それが何になるの?」
ということです。
そして上司の指示を普通に突っぱねてくる人まで出てくる始末です。
もはやここまでくるとモチベーションなんて概念はどこかに消えてしまったかのように錯覚します。
普通に平穏に生活できるくらいに稼げればいい。
余計な責任は負いたくない。
その程度のやる気と村社会の人間関係をいかに上手く渡ろうかということに気をとられている中で高いモチベーションを発揮してもらおうとしていること自体ムリがあるのです。
モチベーションを上げるには?
簡単にまとめると次の3点です。
1.上司からの高評価
2.給料UP
3. 良好な職場環境
しかし上記には重大な欠点があります。
それはすべて自分の力ではどうにもできないことばかりだからです。
すべてまわりがからみます。
だから自分が頑張ったところで現状は変わらないという無力感だけが残るのです。
よって上司ひいては法人がすべきことは明確な評価システムの構築です。
何をすれば評価されるのか、どのような成果が評価につながるのか。
その部分を理解してもらった上でまずはスモールゴールを目指してもらう。
そうやって積み重ねていくしかないんじゃないかと思います。
そもそもいる?
そもそも高いモチベーションって必要なのかという根本論もあります。
なぜなら高いモチベーション=高い生産性とはならないからです。
そもそもやる気なんて存在しない論というのもあります。
だったらモチベーションって一体何?っていうことになるのですが、私の結論としては「あるに越したことはないけれどなくても別にいいんじゃね」です。
モチベーションが高ければ高い成果が出るというのは幻想です。
そこにこだわる必要はないんじゃないかと思います。
だってそこにこだわってしまうと「もっとモチベを、もっとモチベを」という精神論になってしまいます。
仕事に精神論、根性論は不要です。
必要なのは成果の出るシステム構築、しくみづくりです。
そして個人個人が納得がいく評価方法の導入です。
それが用意できればモチベーションに頼る必要はなくなるんじゃないかなと思います。
まとめ
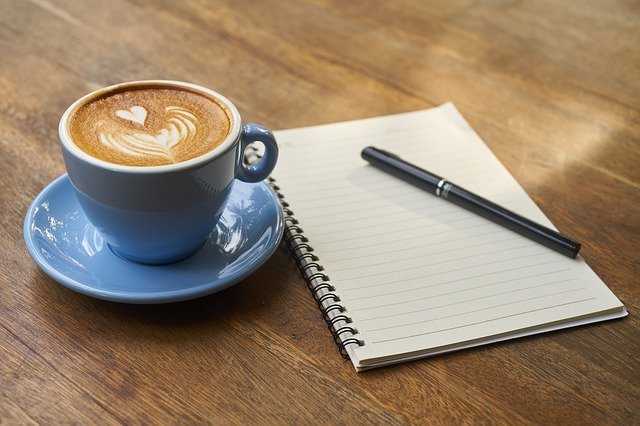
モチベーションの高い医療事務員も少ないですがいます。
ですがそうではない人たちがマジョリティです。
今後高い生産性を出そうとすればどうしていけばいいのか?
それには2つの方法があります。
①モチベーションを重要視するのをやめる。そして誰が抜けても回るシステムづくりに注力する。
②モチベーションの高い人たちを集めて精鋭部隊とする。数に頼らず質を追い求める。
どちらも取り得る方法ではあります。
しかし②の場合働きアリの法則の例もあります。
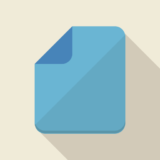 「働きアリの法則」は人間社会の組織には当てはまりません【これはウソ!】
「働きアリの法則」は人間社会の組織には当てはまりません【これはウソ!】
働きアリの法則はあくまでアリの法則なので人間には当てはまらないというのが私の持論です。
ですがどちらにせよ個人に頼るのではなく医事課として全体のシステムとして円滑に回すというところが着地点にはなります。
たとえモチベーションの高い医療事務員が絶滅したとしても医事課として機能し、質の高いアウトプットを出し続けられるのであれば何の問題もありません。
高いモチベーションはあった方がいいのでしょうがこだわり過ぎることもないのではないでしょうか?


