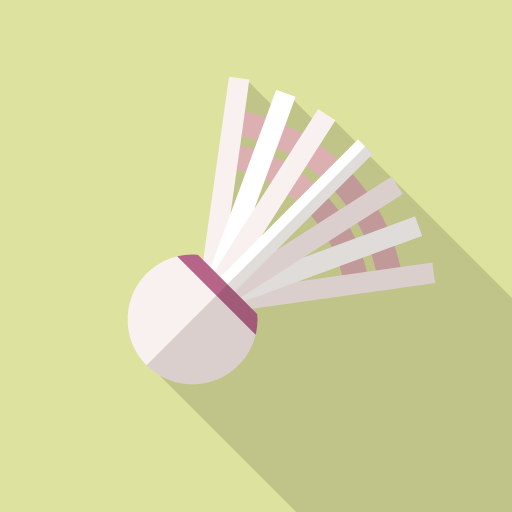医療事務=資格というイメージは今も根強いです。
いまだに医療事務系の専門学校や資格取得のための医療事務講座には一定数の需要があります。
資格を取って即戦力へという流れを推しているのは昔も今も変わりません。
医療事務資格の是非については以前に記事にしました。
 医療事務の資格はいらない?【医療事務歴23年医事課長の答え】
医療事務の資格はいらない?【医療事務歴23年医事課長の答え】 医療事務員が持っていてホントにメリットがある資格とは?【実際は何が有用?】
医療事務員が持っていてホントにメリットがある資格とは?【実際は何が有用?】
また診療報酬請求事務能力認定試験の資格の是非についても記事にしました。
 診療報酬請求事務能力認定試験の資格は必要か?【医事課長の答え】
診療報酬請求事務能力認定試験の資格は必要か?【医事課長の答え】
その記事の結論では不要としています。
今回は私が不要と考える理由を詳しく説明します。
目次
診療報酬請求事務能力認定試験は不要と言い切る大きな2つの理由

結論
2大理由
1.資格用の試験だから
2.病院に認知されていないから
医療事務資格論
これについては私の結論としては出ているので過去記事をお読みください。
簡単にまとめると
・医療事務○○やメディカル△△などのいわゆる医療事務資格はいらない
・診療報酬請求事務能力定試験もいらない
・診療情報管理士・医療情報技師・医療経営士・施設基準管理士などは取っておいた方がいい
・学士は取っておいた方がいい
となります。
この結論には納得いかない人も多数いるのと思います。
特に診療報酬請求事務能力認定試験はいらない、という意見には反対する人も多いかと思います。
これはあくまで個人的な意見ですのでご了承ください。
私自身の感想として「取ってみたけど何の役にも立ってなくね」と思っているだけですので。
これは勤務する医療機関にもよります。
レセプトに関わる者なら必須ですというところや資格手当をつけますというところならば取ればいいと思います。
それ以外のところでは特に取得の必要性があるとは思いません。
2大理由
その1 資格用の試験だから
この資格の試験内容は学科と実技です。
学科は5者択一式、実技は診療録(カルテ)から手書き方式で診療報酬明細書(レセプト)を作成する試験になります。
そして私が不要と考える最大の理由がこの実技試験です。
つまり手書きレセプト試験です。
この手書きレセプト試験は外来から1問と入院から1問出題され、特に入院レセプトが難関と言われています。
確かにゼロの状態から学習してきてのこの入院レセプトの手書き作成は結構大変だと思います。
ですがこれは過去問をくり返しやることによって克服は可能です。
そしてくり返しやっていれば一定のパターンが見えてきます。
どこが出やすいのか、何を押さえておけばいいのかも分かってきます。
要は書けるようになるまでひたすらやり続ければ誰でも書けるようになります。
分からないのはまだその量が足りないんだと思います。
ですがそんな話をしたいわけではないのです。
何が言いたいのかというとそれで試験の問題が解けるようになったとしても、試験が終わればもう一生使うことはないスキルですよということです。
私がこの資格を取ったのはもう20年ほど前になります。
その当時ならまだ手書きレセプト請求というのは確かにありました。
それでもかなりの少数派です。
そして現在となるとそれはもう過去の遺物です。
手書きレセプトに遭遇することはまずないです。
そんな場面は訪れません。
「いや違う。手書きレセプトはないとしても知識として点数の取り方が分かっていないとダメじゃないの?」と言う人がいるかもしれません。
ダメじゃないです。
点数の取り方なんて実務をしていれば誰でも分かるようになります。
そしてここが肝心なところですが、実務ができる人は手書きレセプトは作れますが、手書きレセプトの試験に合格したからといって実務はできません。
これはまったくの別物です。
診療報酬請求事務能力認定試験に合格=即戦力 というわけにはならないのです。
それはこれがまさに資格のための試験だからです。
実際は試験のように拾うべきコストが時系列できちんと書かれているわけではありません。
そして試験に出てくるような診療録を見ることはほぼないはずです。
電子カルテでオーダリングシステムがスタンダードとなった現在において診療録から拾う、手で書くなんてタスクは当然なくなってくるわけです。
さらにレセプトチェック自体がICT化されつつある現状があります。
もはや人の目でレセプトを見ることさえもいずれはなくなります。
この未来はそう遠くないはずです。
今ですらレセプトの目視点検をなくしている医療機関があるくらいです。
今後その波は大きく広がっていくことになると思います。
今後の医療事務は完全にAI、ICT化への道を突き進むことになります。
将来的にはレセプト関連の業務で人が行える部分というのはなくなります。
これは何十年も先の話ではないです。
10年後にレセプト業務がすべて機械化されていてもなんら不思議ではありません。
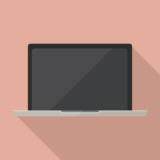 AIが支配?10年後に医療事務の仕事は残っているの?
AIが支配?10年後に医療事務の仕事は残っているの? 【医療事務】15年後には91%の仕事がなくなります【診療情報管理士】
【医療事務】15年後には91%の仕事がなくなります【診療情報管理士】
そう考えたときレセプトの手書き試験が一体何の意味を持つのかは私には分かりません。
その2 病院に認知されていないから
まず最初にこれは病院によってかなり変わってくるというのは断っておきます。
医事課の職員の大半が取得しているというところや、取得者には資格手当をつけますというところは今回の話からは除外します。
そういうところの人は頑張って取得を目指したらいいと思います。
ですがそのような病院ってどのくらいあるものなんでしょうか。
私の感覚でいうとそんなに多くはないと思います。
むしろ「その資格ってそんなに価値あるの?」って思っていたり「それどんな資格?」って思っている病院幹部の人の方が多いと思います。
医療事務の中では結構メジャーな当資格ですが病院全体でみればほぼ誰も知りません。
医事課以外の他部署の感想としては「事務系だけが国家資格じゃない」というこの1点です。
昔私が取得した頃は当資格がいずれ国家資格になるんじゃないかというテキトーな噂も流れていました。
現在この試験を主催する日本医療保険事務協会は内閣府認定の公益法人となっています。
ですので当資格は公的資格という言われ方もしています。
公的資格だから他の医療事務の民間資格よりは格が上と思っている人もいるかもしれません。
ですが私がここで言いたいのはそういう問題ではありません。
医師や看護師、薬剤師、診療放射線技師は業務独占資格です。
また理学療法士、作業療法士、管理栄養士などは名称独占資格です。
つまり無資格で業務を行ったり、無資格で名称を名乗ると処罰対象となります。
資格取得は大前提となります。
ですがそもそも医療事務に資格取得が大前提なものなんてありません。
無資格で仕事はできます。
そうなれば当資格を取るメリットは何なのかということです。
手当がつくとかを除けば私が考えるメリットはたった1点です。
それは資格取得のために勉強したというプロセスそのものです。
当資格は不要と言っていますがそれに費やした勉強過程は不要とは思いません。
それは自分の血肉となって必ず役立つはずです。
でもだったらそれは資格関係なく日々自分でやることも可能です。
しかしモチベーション的にきついというのであればとりあえず資格取得を目指すという目標を置くことはありだと思います。
それ以外の理由ではもう目指す理由はないと思います。
ですのでまとめますと、病院の認知が高いところの人は取得のメリットはありますがそうでなかったら取る必要はないと思います。
まとめ

最後に今後もこの資格試験を続けるというならばこうしたらいいのに、ということを述べておきます。
それは実技試験の廃止です。
前述したとおり手書きレセプトの試験なんて時代遅れすぎます。
まさに試験のためだけの科目です。
資格と実務を直結したいなら実技試験をなくしてすべて学科にするべきです。
実務に活かしたいなら点数表を読み込むスキルを上げるべきです。
診療報酬請求の解釈能力は今後も重要です。
そして改定ごとに内容は変化しますが大事なことはいかに調べられるスキルを上げておくかということです。
「これは点数表のここに書いてあったなあ」とか「これは療養担当規則のこの部分かな」などということを自力でたどりつけるようにしておくことが大切です。
点数表の中身を覚える必要はないです。
このご時世ググればすべて出てきます。
必要なのは調べ方を知っているかどうかということです。
診療報酬の点数表の内容は膨大です。
改定ごとにどんどん点数表自体が分厚くなってきています。
しかし改定ごとにまるっきり変わってしまうなんてことはなく、一部変更され追加され削除されそのくり返しです。
ですのでたとえ昔と内容が変わっていても「これはここらへんに書いてあった」とか「疑義解釈でこう示されていたっけ」ということが分かっていれば求めるべき正解にはたどり着けます。
必要なのは知識よりも検索手段なのです。
この先必要なのは覚えておくことよりも考え方や調べ方です。
そういう意味では当資格試験はすべて診療点数早見表をひかせる問題にしてしまった方が将来には役立つと思います。
少なくとも手書きレセプトの練習をするよりもよっぽど有益だと思います。
ですが一介の医療事務員のたわごとなど誰も聞く耳を持たないでしょうからこの先も試験内容はこのまま続くことでしょう。
診療報酬請求事務能力認定試験とうたっていますがどれくらい能力認定できているのかは疑問です。
この試験のために半年間勉強するくらいなら半年間実務に入った方がよっぽどスキルアップできると私は思います。
最終結論としては医療事務資格に何か期待するのはやめときましょう、ってことです。