古い話で恐縮ですが1995年に「変わらなきゃ」という言葉が流行語になりました。
これは日産のCMでイチローが言ったキャッチコピーです。
当時彼は首位打者でしたので何も変わる必要もないんじゃないかとも思えるのですが、変わっていかないことには成長なんかない、成功するにはチャレンジし続けろというメッセージはその後の彼の生きざまからまざまざと教わることになるわけです。
今回はこの「チェンジ」こそが大事、そしてわれわれ世代こそが実行していかなければ自分にも組織にも良くないよねという主旨で述べていきます。
 ごまお
ごまお
目次
40代こそ変わらなきゃ【ゆでガエル理論とおたまじゃくしの死】

結論
動けるカエルになります。
ゆでガエル理論とおたまじゃくしの死
ゆでガエル
組織変革ではおなじみの寓話にゆでガエルの話があります。
カエルを熱いお湯に入れると驚いて飛び上がります。
しかし常温の水に入れて徐々に水を熱するとその温度変化に気づかずゆで上がってやがて死んでしまうというたとえ話です。
このカエルを組織のなかにいるメンバーとしてよく組織変革の話では引用されます。
つまり組織の中のメンバーが組織内でダメになっていく過程も同じことだということです。
徐々に加熱されてはいるけれど気づかず知らぬ間にゆで上がっているカエルは周りの変化に気づかずだんだんと腐っていってしまう組織内の個人そのものだということです。
医事課でいえば
・新たなスキルアップなど一切アタマにない医療事務員
・現状のレセプトスキルでこの先もやっていけると思っている担当者
・昔からの申し送りをそのまま信じている担当者
・他部署ともめるのがイヤだから問題を先送りする担当者
・プレイングマネージャーから脱却できない管理職
・保身に走る管理職
・前例がないことで踏み出さない上層部
などがこれに当たります。
現状維持バイアス
基本的に人間は変化することを嫌います。
変化を恐れるのは人間の本能です。
ですのでどうして現状維持バイアスというものが働きます。
現状維持バイアスとは、変化によって得られる可能性があるリターンよりも、それにより失う可能性のあるリスクに対して過剰に反応してしまう傾向をいいます。
これは程度の差こそあれ誰もが持っている人間の本能なのです。
人は何かによって得られる利益よりも、そのことで生じる損失の方がすごく大きなものとしてとらえているのです。
ですので変化することで失うことをめちゃめちゃ恐れます。
その結果「変化するくらいなら現状維持の方がトク」という現状維持バイアスが発動するのです。
ですがここで気づかなければいけないことは、変化しなければ現状維持さえもできないということです。
現状維持と思っているのは自分だけで、周りが変化しているのに自分だけがとどまっていれば下降していくのは当然です。
ですがその下降しているということがわからない、つまりゆでられていることに気づかないカエルということです。
対策
現状維持バイアスまみれの私たちがどうやったらそこから抜け出せるのか?
その対策案としては次の2点があります。
・変化した方が得と思わせる
・変化しないと危険と思わせる
結論からいいますと、どちらもほとんど効果は期待できません。
これは私の能力の低いアタマで考えた結果ですので有能な人であればきちんとした答えを示してくれるとは思います。
またはほかの選択肢も考え出してくれることでしょう。
ですが現状病院の医事課という職場限定で考えるのならば、変化させるということはかなりハードルが高いということはまぎれもない事実です。
ここからは完全に当院においての私個人の感想ですので一般の病院の医事課とは切り分けて聞いてください。
まず病院全体が保守的です。
そして各部署の保身が強いです。
表面上は連携が大事、協力が大事ということをしきりに言いますが、実際医事課側から改革案を持っていくと反発されることもしばしばです。
そこには先にいった現状維持バイアスも働きます。
もはやそこには全体最適という概念はないのです。
 【病院組織】全体最適はただの理想論です【ホントは部分最適の集合体】
【病院組織】全体最適はただの理想論です【ホントは部分最適の集合体】
完全なる部署最適です。
自部署が少しでも損だと思うことは受け入れられない、そんな思いが根底にあります。
さらにはヒエラルキーの問題。
 病院内ヒエラルキーと医療事務【医事課の役割とポジション】
病院内ヒエラルキーと医療事務【医事課の役割とポジション】
もそもの部署間交渉が対等ではないのです。
パワーバランスの問題です。
そういうことが繰り返されていると医事課の職員の感想は
「自分たちで何かを変えていくことなんかムリ」
「やるだけ労力のムダ」
となってしまうのです。
そう感じている人に対して「変化した方が得」と言っても「そんなのできっこない」となりますし「変化しないと危険」と言っても「何が危険なの?」となるわけです。
医療事務員のモチベーションは総じて高くない、でもそこが問題の核心ではないという話は以前にしました。
 モチベーションの高い医療事務員は絶滅危惧種?【仕事とモチベ】
モチベーションの高い医療事務員は絶滅危惧種?【仕事とモチベ】
ですがそうはいっても一定のモチベーションはないと組織の変革は難しいです。
どんなに外圧を高めてもプレッシャーをかけてもダメなんです。
「人はみずから変わろうと思ったときにしか変わらない」
それが前提なんです。
おたまじゃくしの死
話をゆでガエルに戻します。
ゆでガエルの中には徐々にゆでられていることがわかっている老獪なカエルがいます。
ですがその老獪なカエルは動きません。
なぜなら知っているからです。
「しばらく持ちこたえれば自分は外に出してもらえる。もうすこしの間だけ知らんぷりを決め込んでおけば次の世代に責任を押しつけられる」と。
つまり老獪なカエルとは数年後には自分はこの組織からは抜けているとわかっている人。
それは定年間近の部長かもしれないし、または数年後には転職しようと決めている課長かもしれない。
この老獪なカエルはあと数年すれば、問題を何一つ解決しないまま外に自分だけ出してもらえます。
そしてあとに残されるのはおたまじゃくし(=若い世代)なのです。
動かない老獪なカエルと死んでいくおたまじゃくし。
これはあらゆる組織で起こっているように思います。
政治だってそうです。
2040年問題を議論するのに70歳の政治家がいてはダメでしょう。
将来の年金問題を考えるのに今年金をもらっている世代がああだこうだ言ったって意味がないのです。
自分たちは逃げ切れるのだから。
だったら真剣に考えるはずがない。
医事課に話を戻しても同じことで、老獪なカエルとおたまじゃくしの構図の組織ってきっと多いと思います。
病院経営が厳しくなるとわかっていても今さえ切り抜ければそのあとのことは知らないって思っている100%保身の経営陣、管理職がいないわけがないのです。
そしてそのツケは現在の若い世代に回されるのです。
40代
ここで冒頭の「変わらなきゃ」の話に行き着きます。
私は40代です。
職歴は20年余りあります。
そして老獪なカエルでもおたまじゃくしでもありません。
わかっていて動かないカエルでもなく責任を丸投げされて死んでいくおたまじゃくしでもないのです。
それなりの経験を積んだ動こうと思えば動けるカエルなのです。
これは同じ年代の人に言いたいのですが、40代が一番ポイントとなる世代なのではないかと。
もうここで動けなくなるとゆでガエルまっしぐらなのではないかと。
20代、30代は間違いなく成長できる年代です。
ですがよっぽどの強い意志とモチベーションがないと40代で成長することはかなり難しいです。
というか周りを見るともう成長しなくても特に何とも思ってないという人が多いです。
このままでいいんだと。
それこそ現状維持に躍起になっている人たちです。
でもその人たちこそ気づくべきなんです。
それは下降まっしぐらなんだということを。
確かに20代の頃より記憶力はかなり落ちました。
30代の頃より体力も衰えています。
だからといってここまでの貯金だけでこの先を生き抜くことはかなりのハードモードです。
それも医療事務でです。
明らかにAIとのすみ分けがなされていく、医療経営という視点が最重要となる、ということがわかっていながら現状維持を選ぶということは、ゆでられて死にますと言っているのと同じです。
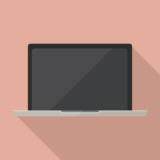 AIが支配?10年後に医療事務の仕事は残っているの?
AIが支配?10年後に医療事務の仕事は残っているの? 【医療事務】15年後には91%の仕事がなくなります【診療情報管理士】
【医療事務】15年後には91%の仕事がなくなります【診療情報管理士】
この先も医事課で生きていくというのなら、40代こそ変わらなきゃと思うべきなのです。
まとめ

常に昨日を超える。たたかうべきは自分自身。
私はいつもそう思っています。
自分ひとりの力では医事課を大きく変えることはできないかもしれない。
でもチェンジするためのチャレンジはやり続けます。
他人を変えることはできなくても、影響を与えられるようにはなりたい。
まずは自分で動きそして周りを巻き込んでいく。
小さな変化を起こし続け医事課としての成果を出せるように愚直に進み続けます。
 ごまお
ごまお


