以前に働きアリの法則について書いたことがあります。
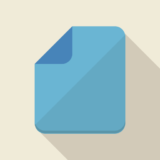 「働きアリの法則」は人間社会の組織には当てはまりません【これはウソ!】
「働きアリの法則」は人間社会の組織には当てはまりません【これはウソ!】
働きアリの法則とは別名2対6対2の法則ともいいます。
簡単に説明すると組織において、できる人、フツーの人、できない人の割合は2割:6割:2割というように偏るよという法則です。
そしてできる人2割が全員いなくなると残りの人たちの中でまた2対6対2に再編成されるんだよ、という法則です。
その記事ではそれはあくまでアリの法則であって人間の組織には当てはまらないと述べました。
ですが管理職として今まで見てきた感想としては「そうはいっても一定の偏りはどうしても出てきてしまうよね」というのが率直な感想です。
それは2:6:2にはなっていなくても1:7:2だったり3:5:2だったりさまざまです。
今回はこの偏りに対してどうとらえ、どう回していくべきなのかという点について述べていきます。
 ごまお
ごまお
目次
【これはガチ】フツーの医療事務員こそ超重要!【2対6対2の法則】

結論
医事課を牽引しているのはフツーの医療事務員です。
できる人、フツーの人、できない人
そもそも何をもって医療事務ができる人、できない人の区分けとするのかの判断は人それぞれです。
これは相対的なもので有能、無能とはその時々で変わる基準や環境でどうにでも変化します。
ですので一概に明確な線引きはできません。
このあたりのことは以前にも述べました。
 有能と無能と無力【医療事務仕事論】
有能と無能と無力【医療事務仕事論】
ですが今回の内容ではできる人、フツーの人、できない人の定義は次のようにしておきます。
・できる人→病院収益の最大化においていちじるしく戦力になる人
・フツーの人→病院収益の最大化において戦力になる人
・できない人→病院収益の最大化において戦力にならない人
フツーの医療事務員はほったらかし?
ここからは管理職目線で述べていきます。
管理職に求められる役割の1つに部下の育成、モチベーション管理があります。
そのためには部下を見る十分な観察力、注意力が必要です。
そしてこの先がポイントでそのリソースはできる人、フツーの人、できない人に対して均等に割り振られてはいないのです。
というかどうしても均等にはできないのです。
その割合は私のおおよその感覚でいくと5:1:4ぐらいです。
つまりできる人に対する観察、注意資源が5でフツーの人に対しては1、できない人に対しては4というわけです。
なぜここまで偏ってしまうのかを説明します。
できる人
この人は医事課の主力となる人です。
仕事はできます、たしかにできます。
そして仕事に対するモチベーションも十分高い。
だったら任せておけばいい、というわけにはいかないのが難しいところです。
いちじるしく戦力になるがゆえ、常にそれに見合う仕事を与え続ける必要があるのです。
周りと同じような仕事をやってもらっているだけでは、その人の価値というのが薄まってしまうのです。
そして何よりそれではその人のモチベーションが維持できない。
以前にモチベーションの高い医療事務員は絶滅危惧種である、だが別にいいんじゃね、ということを書きました。
 モチベーションの高い医療事務員は絶滅危惧種?【仕事とモチベ】
モチベーションの高い医療事務員は絶滅危惧種?【仕事とモチベ】
ですがそうはいってもモチベーションが高い人は一人でも多くいた方がいいのはあたり前の話です。
そして医療事務では一度下がったモチベーションを再び上げさせることは至難のわざです。
それはまわりのネガティブに引っ張られるからです。
 受動ストレスを避けよう【ネガティブに引っ張られるな!】
受動ストレスを避けよう【ネガティブに引っ張られるな!】
マラソンと同じで一度歩いてしまうと再び走り出すことはなかなか難しいのです。
ですのでマラソンでの完走のコツは遅くてもいいから走り続けることなのです。
決して立ち止まらないということです。
仕事も同じことで、走り続ける人はそのまま走り続けさせなきゃいけないってことです。
歩くことを覚えてしまうともう走れない。
まして超戦力になってくれる人であるならなおさらその高いモチベーションは維持してもらわないと困る。
そのためにはどうしても結構な割合の観察、注意資源は投入せざるを得ないのです。
できない人
できない人に観察、注意資源を割くというのはなんとなくわかることだろうとは思います。
語弊を恐れずにいうと要するに危うい人だからです。
戦力にならずともプラマイゼロならまだいい方です。
だいたいはマイナスの結果となります。
以前にも取り上げたことがありますがある組織論があります。
これはドイツの軍人ハンス・フォン・ゼークトが提唱した組織論です。
そこでは軍人を4つに分けています。
ひいては人間を4つのタイプに分けています。
有能な怠け者
これは前線指揮官に向いている。
理由は主に二通りあり、一つは怠け者であるために部下の力を遺憾なく発揮させるため。
そして、どうすれば自分が、さらには部隊が楽に勝利できるかを考えるためである。
有能な働き者
これは参謀に向いている。
理由は、勤勉であるために自ら考え、また実行しようとするので、部下を率いるよりは参謀として司令官を補佐する方がよいからである。また、あらゆる下準備を施すためでもある。
無能な怠け者
これは総司令官または連絡将校に向いている、もしくは下級兵士。
理由は自ら考え動こうとしないので参謀の進言や上官の命令どおりに動くためである。
無能な働き者
これは処刑するしかない。
理由は働き者ではあるが、無能であるために間違いに気づかず進んで実行していこうとし、さらなる間違いを引き起こすため。
ゼークトは組織の1番の害は「無能な働き者」であるとしています。
この人たちの最大の特徴は一切のメタ認知が効かせられないという点にあります。
だから勝手な自己判断や思いこみをしてみたり、自分の間違いや失敗を認められない人になってしまいます。
そして一番危うい点が「自分は仕事ができる」と思っているということです。
こうなってしまえばどうしてもそれ相応の観察、注意資源を投入し適時修正させていく必要がでてきます。
ですのでここも避けられないのです。
フツーの人
前述したとおりできる人、できない人にかなりのリソースを割かなければ組織はスムーズに回らないのです。
そしてここで割を食うのがマジメにコツコツ仕事をこなすフツーの人です。
そして本来ここの部分の人が大部分なわけです。
そうすると大部分に観察、注意資源を投入できない無能な上司というのができあがるのです。
そして実際そうなっていたとしても上司自身はそのことには気づかない。
上司としては、部下の育成、モチベーション管理については一生懸命やっていると自分では思っています。
ですが大部分のマジメなフツーの部下からすれば、自分に目を向けてくれているとは全然思えないわけです。
そしてえてして自分の保身のためだけに動いているようにしか見えなくなるのです。
それは自分の承認欲求が満たされないがために大きくバイアスがかかっている状態ともいえます。
「なぜあの人ばかりに任せるの?」
「あの人ばかりを叱っているなあ」
これらは真逆の行動ですがフツーな部下からすると同じくくりになってしまうのです。
つまり自分は上司の視野には入っているのかという疑念です。
そしてその疑念がしだいに自分なりの確信に変わりもうそのバイアスは取り去ることはできなくなる。
結果モチベーションは下がっていく。
しかしこの状況は上司視点だとまったく違うのです。
自分が指示、指導、叱責せずともマジメに粛々と仕事をこなしているフツーのその人たちが、自分にそこまでの不信感があるとは思っていない。
言わずとも確実に成果が出続けているのであれば、特に問題はないと思っている。
ましてその人たちのモチベーションが下がっているとはつゆほども思っていない。
なぜこんなとらえ方になってしまうかというと、あまりにもできる人、できない人に引っ張られてしまうからです。
そこを押さえることが一番重要だという想いが強いのです。
重要なのはフツーの人
2対6対2の法則ではできる人の2割を取り除けば、残りの人の中でまた2対6対2に再編成されるとされています。
ですがここでひとつ疑問なのがそれらのアウトプットレベルは同じなのかということです。
ここの検証をしている解説を見たことがありません。
2対6対2の法則でよく聞く結論は、結局2対6対2に再編成されるのだから上位の2割も下位の2割も取り除いたところで一緒のこと、というものです。
しかし出せるアウトプットの質が変わってくるのであれば一緒のことではないのです。
上位の2割を除いてアウトプットレベルが下がるのであれば全然同じではないし、反対に下位の2割を除いてアウトプットレベルが上がるのであればその意味はあるのです。
医療事務でよくある話で次のようなのがあります。
その医事課で一番レセプトに詳しい大ベテランが退職することになりました。
↓
本人「私が抜けたらしばらくは結構きついかもしれないな」
周り「これ現場回るの?大丈夫か?当分しんどいかも・・・」
↓
結果 何も問題なし。今までどおり回っている。
何が言いたいのかというと、結局はシステムが機能していれば現場は回るということです。
逆に言えば個人に依存している限り高いアウトプットレベルはのぞめないということです。
2対6対2の上位2割だろうが下位2割だろうがそこを除かれたところで揺るがない組織というのは、真ん中んのフツー部分がしっかりしている組織なんだということです。
変な言い回しですが、フツーな人が優秀なんです。
そこをなおざりにしている組織は継続した安定的なアウトプットは出せないのです。
ここからは私のかなり偏った個人的見解なのでテキトーに聞いてください。
この2対6対2の法則でいうと、医療事務に関しては上位の2割はほぼいないと思います。
今回この上位の定義は「病院収益の最大化においていちじるしく戦力になる人」としています。
そもそもいちじるしく戦力になるとはどういう状態かがあいまいですが、それこそ査定対策のノウハウであったり施設基準の観点からの経営的アプローチであったりということになります。
そしてそれらはもはや医療事務の一担当者レベルの能力、裁量を超えていく話になります。
もはや管理職、もはやゼネラリストということになります。
ですので上位2割はかなり高いレベルでありあまり現実的ではないということです。
そして反対に下位2割ですが、こちらは病院によっては1割であったり3割、4割だったりするかもしれません。
ここが0割なんてところはまずないと思います。
どうしても出てきてしまう、これは事実です。
ここをどうするかということはもちろん大事な点ではありますが、そんなにリソースを注ぐところでもないなとは思います。
その理由ははっきりいって効率的ではないからです。
生産性が悪すぎます。
かける手間に見合うリターンはほぼのぞめないゾーンなのです。
それよりも手を入れるべきは中間ゾーンなのです。
大部分の医療事務員はフツーでマジメな人たちです。
しかしその人たちの中でも2つのパターンに分かれます。
・フツーでマジメでモチベが高い
・フツーでマジメでモチベが低い
私の感覚だけでいいますとその割合は、前者2割、後者8割です。
そして間違いないのが前者から後者へは移動するが、後者から前者への移動はほぼない、ということです。
働いている途中から謎の意識革命によって低かったモチベーションが急に高くなる人をいまだかつて見たことがありませんし今後も見ることはないと思います。
そんなことはほぼ起こりえないのです。
反対の例は山ほどあります。
高かったモチベーションが落ちてしまったという例、そしてそれは再び上がることがないという例。
ここで大事なことは、現在まだ高いモチベの人をいかにその状態でキープさせるかということです。
そしてその人たちの割合はそんなに多くはない。
ざっくりいうと、この少数のフツーでマジメでモチベが高い人たちが引っ張る形でそこに多数のフツーでマジメでモチベが低い人たちが続き、医事課を牽引しているのです。
ですのでフツーの医療事務員の人たちが一番重要なのです
まとめ

管理職になると昔自分が上司に持っていた視点や感情をいつしか美化していることに気づくことがあります。
それは「あのときはこう思っていたけど、実際管理職って大変なんだよね」とか「上司には上司なりの苦悩とか苦渋の決断なんてことも多いんだよね」という自己弁明、自己弁護だったりします。
しかしそれが一番いけないことだよなっていつも反省します。
だってまさにあの時の自分が今の部下なのだから。
だから当時の想いを美化することなく、ありのまま自分にぶつけることが必要だと思っています。
「上司は保身のかたまり」
「上司は自分を重視していない」
「上司の見方は常に偏っている」
あのときの自分はそう思っていました。
だったら今の自分はきっとそう見られているに違いない。
そこから思考を出発させないときっと見誤る、いつもそう思っています。
だからこそ均等に見る目、広い視野、それがないと始まりません。
2対6対2の法則の惑わされず、常にフラットな視点で多角的に人やものごとを見ていきたいと思っています。
そしてフツーの医療事務員の人の重要さを再認識し彼ら、彼女らのモチベーション維持に貢献できる上司でありたいと思います。
 ごまお
ごまお


