以前にリーダーシップについていくつか記事にしたことがあります。
 【医療事務とリーダーシップ】リーダーシップとはなんぞや?【採用基準】
【医療事務とリーダーシップ】リーダーシップとはなんぞや?【採用基準】 圧倒的なリーダーシップなんていらない【リーダーとリーダーシップ】
圧倒的なリーダーシップなんていらない【リーダーとリーダーシップ】
そこでの結論は
・医事課が成長していくためにはメンバー全員がリーダーシップを持つべき
・リーダーシップというのはメンバー全員が体験すべきものであり学んでおくべきもの
ということでした。
つまり部署のリーダーは一人でもリーダーシップは全員に必要だということです。
ですがこれはあくまで理想論です。
そのような医事課はなかなか存在しません。
いくらリーダーシップ体験はみんなするべきといっても、全員が同じようにその機会にめぐり会うとは限りませんし、リーダーシップ体験なんかしたことがないっていう人も当然いるわけです。
結局ほとんどの組織が一人のリーダーとその他大勢という図式に落ち着いてしまいます。
そしてそもそも「リーダーって何なんだ」「どんな役割を果たす人がリーダーなのか」というところがすごくあいまいです。
個人ごとでその認識がバラバラです。
今回はリーダーって何なのさっていう点について述べていきます。
 ごまお
ごまお
目次
【リーダーの役割】あなたの上司は真のリーダーなのか?

結論
リーダーとは目標達成のために必要なことをする人です。
リーダーとは?
リーダーの役割
医事課のリーダーといえば誰なのかといえば、医事課長を指す場合もあれば、病院の規模によってはそれが医事部長となっている場合もあり、また違う役職者になっている場合もあるかもしれません。
ですがその人たちは総じて管理職と呼ばれる人です。
そしてそもそもこの管理職というポジションの本来の役割とは何なのかというと、部下の管理、監督、マネジメントなわけです。
ならば医事課のリーダーはそこに専念すればいいのかというとそういうわけにもいきません。
なぜか?
それは組織の管理、監督だけに専念していては部署の改善、成長はのぞめないからです。
経営層は現場を知らない、現場は経営層の想いがわからない。
上からの指示、下からの意見、それらを調整しつつも進捗はとどこおってはいけない。
現場がオーバーワークにおちいっていれば、対応策を考えねばならないし、適時フォローをしなければならない。
そういうさまざまな状況に対応していくには、管理する側という一方通行的な視点では柔軟に対応していくことは難しいのです。
立場は管理者でありながらも、現場視点がないと間違いなく見誤ります。
つまりリーダーとは常に医事課の全体最適を考えなければいけない立場です。
 【病院組織】全体最適はただの理想論です【ホントは部分最適の集合体】
【病院組織】全体最適はただの理想論です【ホントは部分最適の集合体】
病院全体として全体最適とは非常に難しい課題だとは以前に述べたとおりですが、少なくとも医事課としての全体最適は成し得ないと医事課のリーダーとしての役割は担えていないわけです。
ですがそれはなかなかに難しい。
そして医事課のリーダーとなるとどうしてもプレイングマネージャーにならざるをえなくなります。
そもそもマネージャー業をしているだけで平穏無事に回るほど医事課業務はたやすくないし、業務自体も幅広い。
ですが本来リーダーというのは取り組むべきリーダーならではの仕事というものがあります。
そしてそれは成果を出すために最優先で取り組むべきことです。
またそれはこの先の医事課のビジョンを描き進めていくことだったりもするわけです。
リーダーは雑用係?
医事課の一担当者から主任へ、係長へ、課長へとなった場合、割に合わないなと思うことが出てきます。
それは業務量が余計にふくらんでいくことです。
先ほどあったプレイングマネージャーという役回りです。
そしてさらに組織運営の要となるところはリーダーが行うべきだという暗黙の了解により、ますます煩雑な業務が増えていきます。
そうこうしているうちに医事課のビジョンを描き、人を育成し、チームビルディングを行うなんてことには手が回らず、日々の業務に忙殺される無能なリーダーができあがってしまいます。
リーダーが本来取り組むべき創造的な仕事ができず、ルーチンワークに追われる毎日というわけです。
はっきりいってこれではビジョンを描くなんてことは不可能です。
そもそもそんな時間がとれません。
特に病院というところは生産性の概念があるのかないのかわからないようなところで、たとえば会議、委員会、ミーティングがやたらとあります。
それも実のあるものだったらまだいいのですが、ほとんどが時間のムダです。
これはその会議自体を否定しているわけではなく、時間の使い方がおかしいといっているのです。
会議は議論する場ですし、ものごとを決定する場です。
でもそんな会議は少ない。
何も決定せず、何も進展しない、そんな会議も中にはあります。
たとえそんな会議でも部署長は出席せよとなっていれば出ないといけない。
出たところでどうなる?何も影響しない、そんな事例は山ほどあります。
この会議に1時間必要なのか?
30分で十分なのでは?
そんな会議も多いです。
ですが過去からの慣習に従うというところは崩れず、いつまでたっても1時間です。
その時間が出席者たちの生産性をいちじるしく下げているという認識は多くの人にはありません。
そして何よりそんな会議に出席するリーダーのモチベが高いはずがありません。
プレイングマネージャーの良し悪し
今や管理職がプレイングマネージャーというのは当たり前の世の中です。
現場を知っているということで現場の状況、現場感というものを感じることができ、それにより部下への指導もしやすいというメリットがあります。
これは確かに大きいです。
ですがまずプレイングマネージャーというものが諸刃の剣です。
これは両方を兼ねているからこそ、マネージャーという能力を集中して伸ばせない場合があるからです。
「名選手名監督にあらず」とは以前に述べたとおりです。
 【即解決】医事課を良くする一番の方法は上司を変えること!?
【即解決】医事課を良くする一番の方法は上司を変えること!?
そもそもプレイヤーとマネージャーの能力はまったく別物です。
そして管理職に就く人がなぜその役職に抜擢されたのかというと、個人としての成果が認められたからです。
これは当たり前のことですが、それと組織としての結果を出すということでは、求められているスキルが全然違います。
個人としては優秀、でも人を育てることはできない、とか、逆に個人の能力としては普通だが部下の使い方が超上手いなんて人もいるわけです。
でも実際は個人としての成果を出せた人、認められた人が管理職になります。
そして何のマネジメントスキルもない人であってもゼロからそれを学んでいくのです。
そうなった場合、プレイングマネージャーではマネージャーとしての能力がまったく上がってこない場合だってありえます。
プレイングマネージャーであってもほぼほぼプレイヤーという人であれば、管理職として成長することはすごく遅くなるのです。
プレイングマネージャーであってもいいのですが、かなりマネージャー寄りでないと良いリーダーにはなれないのではないでしょうか。
医事課の理想型
この先の医事課を良くしていくために日々上司は試行錯誤しています。
ですが冒頭の話に戻るのですが、一人のリーダーとその他大勢という図式をまず変えることこそが最もすべきことです。
その図式を変えない限り、管理職がすべての重責を担う、そして雑用もこなすといったルーチンワーク症候群から抜け出せません。
そしてその状態では医事課のビジョンを描くなんてことは到底できません。
だったらどうしていくべきか?
まずはナンバー2、ナンバー3の育成です。
リーダーが思い描く絵を全員がいいと思うことなんてあり得ません。
反対する人、従わない人は当然出てきます。
それが組織です。
以前に働きアリの法則を紹介しました。
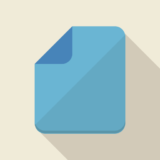 「働きアリの法則」は人間社会の組織には当てはまりません【これはウソ!】
「働きアリの法則」は人間社会の組織には当てはまりません【これはウソ!】
人間の組織でもそうなる可能性は大いにあります。
だったら間違いなく下位の2割は反対ですし、中間層の6割も積極的には従いません。
完全に賛成なのは上位2割しかいない可能性もあります。
でもそれならそれで上位の2割をフルに活用すればいいのです。
そしてそのためには、ナンバー2、ナンバー3の育成が必要です。
この時大事なことは、イエスマンにはさせないことです。
かといって常に意見してくるのもスムーズにことが進みません。
難しいことですが、イエス50%、ノー50%のような人が理想的です。
大切なことはきちんと考える癖を持ってもらうことです。
100%イエスな人も100%ノーの人も言うなれば思考停止です。
それでは成長していきません。
そばにイエスマンがいることは気持ちがいいし楽なことです。
ですがそれでは自分を見失う。
リーダーが裸の王様になったらその組織は終わっています。
そうならない方法、意識をしっかり持つことがリーダーには求められるのです。
あとナンバー2についていうなら、イエス50%、ノー50%の人であっても、おおもとの意見というか方向性の認識合わせは必要です。
その軸さえしっかりしていればその場その場の状況でお互いの判断がブレるということはないはずです。
よきリーダーには必ずよきナンバー2がついています。
リーダーがまずすべきは業務を回すことでも、全員をマネジメントすることでもなく、ナンバー2を育て上げることなのかもしれません。
そしてまたリーダーが認識しておくべきことは、世代交代は必ずあるということです。
権限は委譲していかねばならない、ということです。
40代、50代のおじさん、おばさんが権力を握って医事課を回す時代は過去の話です。
この先のAI・ICT時代を乗り越えていくには20代、30代の人の力が不可欠です。
私は自分の経験、そして知識、ノウハウを少しでも共有してもらって誰かの役に立てればという想いで日々書き綴っています。
特に若い世代には大きな期待を寄せています。
もう私のような固いアタマではこの先の新しい変化にピッタリなアイデアを出すことはかなり難しくなっています。
柔軟な発想、斬新な発想はやはり若い世代の方が優れています。
そのような人たちにとって少しでもヒントとなるようなものを書いていければなと思います。
まとめ

話が少し逸れましたがまとめに入ります。
リーダーとは目標達成のために必要なことをする人です。
そのためにはきついことも、からいことも言うかもしれません。
結局医事課のメンバーがどこまでついてきてくれるのかというのは、成果を出すことがどれだけ大事かということを理解してくれているかどうかにかかっています。
ですがその説明をリーダーはきちんとできているのでしょうか?
法人のビジョンは自分ごととはとらえていても、それを部下にまでしっかり下ろせているリーダーってどれだけいるのでしょう?
「そんなところのフォローまでしている暇がない」というプレイングマネージャーもいるでしょう。
また「部下は上席の指示に従えばいいんだ」という人もいるでしょう。
それぞれの医事課にいろんなリーダーがいます。
正解のリーダー像なんてわからない。
それを探ることはナンセンスなのかもしれない。
ただいえることは、目の前だけを見てはいけないということ。
リーダーも部下も全体の状況を見渡した上で判断しないといけません。
自分の視点だけでは必ず事実はねじ曲がっているはずだ、そう思っておくべきです。
リーダー論をきちんと語るにはやはり高いメタ認知力がマストなのです。
 ごまお
ごまお


