早いもので昨年4月に入職した新人もまもなく職歴1年となります。
当医事課にも2名新人が在籍しており丸1年を迎えます。
最初はつたなかった仕事ぶりも日ごとにいろんなことを吸収し、どんどん成長していく時期でもあります。
そして現に成長していっているなと外から見ていると思うのですが、そばについている教育係は決してそう言い切れないという部分を持っているようです。
今回は教える側の傲慢さというテーマで述べていきます。
目次
あなたも初めからできてたわけではないでしょう【新人ができないと嘆くその前に】
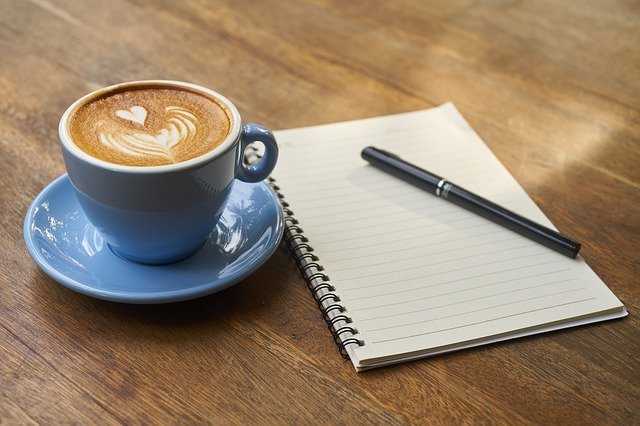
結論
ベテランは自分ができなかったときのことを思い出しましょう。
5年目と1年目
以前に入院係は最長でも5年までとすべき、それ以上はムダに経験を積むだけなので違う担当科なり違う係へ移るべきという主旨のことを書きました。
 【医療事務】入院係は5年で卒業すべき論
【医療事務】入院係は5年で卒業すべき論
医療事務の仕事はかなり細分化できます。
そしてジョブローテーションの意向が弱い医事課だと下手をすると6年も、7年も入院係で同じ診療科担当ですという人も出てきます。
これは外来係でも同様です。
外来レセプトを見続けて10年ですという人にはもう伸びしろなんてないのです。
こんなこと一般企業ならあり得ません。
必ず異動というものがついてまわります。
ですが病院事務では起こりうることなのです。
それも中小の常に人手が足りないところでは、人を埋めるのが精一杯でジョブローテーションなんてとても行う余裕がありません。
私はそんな状況であっても無理矢理にでもジョブローテは行うべきだと思っています。
どうしてかというと、これは繰り返しになるのですが、もう一切成長しなくなるからです。
100%わかる仕事をしていて何を新たに学べるのでしょうか。
どう成長できるのでしょうか。
しかしこの前提には仕事は他者貢献と自己成長ありきという考えがあります。
 仕事って結局お金の為?【医療事務の本音】
仕事って結局お金の為?【医療事務の本音】 他者貢献と自己成長【医療事務の仕事】
他者貢献と自己成長【医療事務の仕事】
そしてこの前提がそもそもすべての医療事務員に当てはまるのかという問題があります。
 モチベーションの高い医療事務員は絶滅危惧種?【仕事とモチベ】
モチベーションの高い医療事務員は絶滅危惧種?【仕事とモチベ】
とても悲しい事実ですが、自己成長なんて必要ないと思っている医療事務員は結構な割合でいます。
自分の食いぶちさえ稼げればそれでいいんだと、それ以上は望んでくれるなという人です。
その人から見ればジョブローテなんてされたらたまったもんじゃないのです。
余計な労力を使ってまたイチから新たな業務を覚えなければいけないのですから。
そしてそんな今の業務に余裕しゃくしゃくの人から見れば、1年目の新人はできなさすぎて困るとうつってしまうのです。
できないことがわからない
今回の記事を書くきっかけとなったのは、そんな余裕しゃくしゃくの教育係との会話からでした。
話している内容は至極真っ当なのですが、それを1年目に要求するのはちょっと酷では?というものでした。
しかし教育係本人は本気でそう思っているようでした。
「なぜできないのかわからない」
「普通ならこれぐらいできていて当たり前」
そういう思いを抱いていました。
これを聞いて思ったのが、できる人はそれができるようになった瞬間にできなかったことを忘れてしまうんだな、できなかったときのことがわからなくなってしまうんだな、ということでした。
しかしこれは私たちが持つ自然な感覚なのかもしれません。
えてして人は過去の出来事を美化してしまいがちです。
それができなくて悔しかったり、つらかったと感じていれば余計にそうなります。
そしてできなさ加減がひどかった事柄であればあるほど、できるようになった瞬間にそのすべてはいい思い出に転化されてしまうのです。
自分がそれまでさんざんできなかったことの記憶は、遠い彼方にほうむられてしまうのです。
さて今回の話で取り上げている新人が配属されているのは入院係です。
これは医療事務の新人育成のスタンダードからは外れています。
スタンダードは外来→入院です。
外来で広く浅く医療事務の概要を知り、そのあとに入院で狭く深く知る。
確かにこれが最もソフトランディングできるコースではあります。
ですが私の考えだと結局すべての業務をジョブローテでまわるわけだから、どこから入っても一緒なのです。
外来レセプトを見ている担当者は入院レセプトは難しいと思っています。
ですがそれは完全に思い込みです。
決して簡単とは言いませんが慣れれば見れるようになります。
だったらなぜ難しいと思っているのか。
それはただやったことがないから、経験していないからという理由なのです。
これはある種の医療事務の業務バイアスです。
新人からしてみれば、外来業務も入院業務もそれが最初の業務ならばどっちも意味不明、わけわからん、なのです。
それを外来業務から行こうが入院業務から行こうが大局から見れば大差ないのです。
しかしそうはいっても入院レセプトの1件のボリュームは外来レセプトのそれとは比較になりません。
やはり狭く深くなのです。
ですので新人で入院係を1年でマスターなんてどだいムリな話なのです。
診療科にもよりますが最低2年は必要です。
それぐらいのスパンで見ておかないと十分な育成は行えません。
新人時代を思い出せ
現在新人教育を担当しているすべての医療事務員の人にそう言いたいです。
自分の新人時代はどうだったのかと。
そんなにあなたは有能だったのかと。
しかしこれはかなりムリな問いかけでもあるのです。
なぜならそれを踏まえた上で教えている人であるならば、「なぜできないのかわからない」なんて言わないからです。
自分の新人時代はこんなんじゃなかった、という美化バイアスが入っているからこそ、そのセリフが出てくるのです。
だから、あなたも新人の頃はそうだったでしょ、と言ってもひびかないのです。
もう優秀だった自分の新人像ができあがっているからです。
だから言い方を変えます。
「新人はできないから新人なのです」
それをできる人に育てあげる役目が教育係なのです。
しかしここでまた一つ疑問が生じます。
いつまで新人なんだと。
人によれば2、3ヶ月までとか、半年までとかさまざまな見方があります。
そして多くの人が思うのが、もう1年も過ぎれば新人ではない。
十分一人前なはず。
ですがここでも思い出してほしいのです。
職歴1年の自分は果たしてどれくらいできていたのか。
十分一人前といえるレベルだったのかと。
きっとそうではなかったはずです。
そしてきっとあなたもあなたの教育係から「なぜできないのかわからない」と思われていたはずなのです。
そこの理解をきちんとすべきです。
私は何もそれを踏まえた上でもっと優しく教えてあげてと言っているわけではありません。
厳しい見方をするならそれはそれでいいのですが、ちゃんとした比較根拠を持っておきましょうっていうことなのです。
自分の新人時代は棚に上げておいて、教育係レベルの視点から指導されると新人はたまったものではないということです。
十分経験を積んだベテランなら、こういう言い方をすれば相手がどう思うかとか、こういう見方は一方的だなというメタな視点に立てないといけません。
このブログでは常に出てくるメタ認知力の向上です。
あまりにも自分視点の教育係が多いのではないかと思うのです。
新人時代を思い出せと言ってもベテランであればあるほどもうよくわからないはずです。
だから別の言い方をします。
「あなたも最初は確実にできなかった人なのです。
ただそれを忘れてしまっただけなのです。
それを認識してください。」
まとめ

今回の内容は一方的に教育係を批判しているように受け取られるかもしれないですが、そうではないです。
新人教育の問題点は教わる側、教える側双方にあります。
どちらか一方の問題ではありません。
そして新人は自分の至らなさを自覚しているので謙虚さを持ち合わせていますが、えてして教育係にはその謙虚さが欠如している場合が往々にしてあります。
つまり医療事務教育係の傲慢さがそこに出るのです。
そして最も問題なのは、そのことを当の本人はまったく自覚していないということです。
できない新人のレベルの低さを嘆くことはあっても、自分の指導レベルの低さを嘆くことはないのです。
結局教育係は教え方を教わってはいないのです。
すべて自己流。
それを裏打ちする根拠となるものは自身の経験のみ。
そんな人に教わるということはすごくリスキーなわけです。
できる教育係に育てられた新人はできる人となっていき、できない教育係に育てられた新人はその程度の人材にしか育たない。
完全なる教育係依存なのです。
もういってしまえばくじ引きと一緒です。
いい教育係を引くか、そうでない教育係を引くか。
すべては運しだい。
これは冗談ではなく本当にそうなってしまうのです。
だったら事前にその人選を上司がしっかり行っておけばいいのではないか?
その指摘は当たってもおり、はずれてもいます。
なぜなら実務ができる人イコール教え方が上手いとはならないからです。
人選をしても仕方ないのです。
実務オンリーできた人の教育係としてのポテンシャルなんて未知数なのですから。
やらせてみてはじめて教え方が上手い、下手がなんとなくわかるという程度なのです。
これもわかる、ではなくなんとなくわかるというぐらいです。
そしてこれは単純ではなくて、はたから見ていて教えるのが上手いと感じるのと、実際教わっている新人が感じている教え方の上手い、下手は一致しません。
それは当たり前の話で、教えている人もはたから見ている人もみんなわかっている前提だからです。
対して新人はわからない前提です。
意見が一致するはずがありません。
そこを「頑張りが足りない」「学習できていない」と切り捨てるのは簡単です。
ですがそのツケは必ず私たちに返ってきます。
「この子はできない」と判断するのは一番最後にすればいいこと。
途中で自分で勝手に線引きしている場合ではない。
そこに至るまでにやれることはやったのか?
メタな視点を持っていたのか?
将来の医事課のエースと期待して育てようとしていたのか?
傲慢な教育係にはその視点が欠けています。
そして何より欠けているものは、自身もそれによって成長できるという視点です。
教えながらも学ばないといけないのです。
ですがそう思える人は少ない。
傲慢なベテランになってはいけない。
でも傲慢なベテランは自分が傲慢だとは一生気づかない。
だったらそうなる前に気づかないといけないのです。
そのためには自分ができなかったときのことを思い出すことも大事なことなのです。


