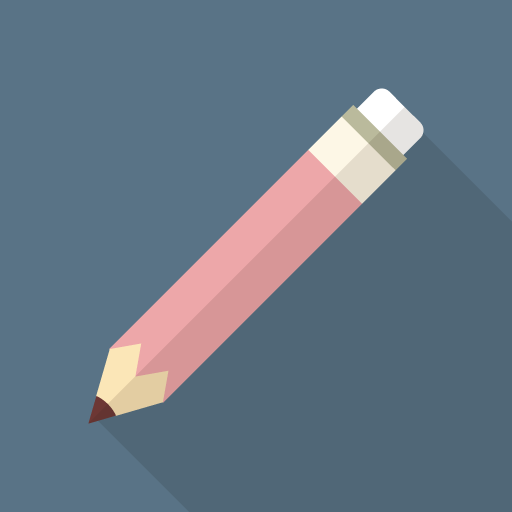今回のタイトルは人によっては「そのとおり」と思うでしょうし、逆に「どういうこと?」と思う人もいるかと思います。
医事業務ではしばしば人手不足という状況が訪れます。
そのとき一体どうすることが正解なのか、どういうスタンス、マインドでのぞむべきなのか。
今回はその点にフォーカスして述べていきます。
 ごまお
ごまお
目次
【コレってホント?】ひとが足らない場合には仕事を回すな!?

結論
それは状況による。しかし、どちらにせよ中長期的な視点が必要不可欠です。
医療事務員軽視論
病院は労働集約型産業です。
つまり収益を上げるには、診療報酬の点数を取っていくには人は集めなければならない。
必要な専門職はどんどん採っていく必要があります。
しかしこれには医療事務員を除いて、という注釈がつきます。
それ以外の専門職は施設基準を満たすために一定数の人数が絶対必要です。
しかし事務系でも中には一定の人数が必要なところもあります。
それは医師事務作業補助者です。
ここだけは決められた人数を配置しておく必要があります。
しかしそのほかで事務員の数を求められることはありません。
診療情報管理士が何人必要であるとか医療情報技師が何人必要であるとか、医療経営士が必要であるとかの算定要件は残念ながらありませんし、今後新たに生まれる可能性も限りなく低いです。
ですのではっきり言ってしまえば、医事業務がきちんとまわるのであれば医療事務員は何人でも構わないのです。
そして経営陣からするとその数は少ないに越したことはないのです。
そうやって限られた数の中ギリギリでやりくりしていると、ある日突然一人が退職することによってすべてが崩壊しかねない危機へと至る場合もあります。
そこには医療事務員ごときにそんなに配置リソースを割くわけにはいかない、という経営陣の判断と、足りないなら足りないなりに回せ、というほぼ丸投げのような傲慢さも見え隠れします。
いってみれば医療事務員軽視です。
これは一概にどこの病院でもそうであるとは言えません。
ここはヒエラルキー問題とも関連するのですが、病院ごとに部署間のパワーバランスというのは全然違います。
 病院内ヒエラルキーと医療事務【医事課の役割とポジション】
病院内ヒエラルキーと医療事務【医事課の役割とポジション】
ですので医事課の位置が高い病院では十分な配置リソースが割かれます。
そういうところでは少々退職者が出たところで十分な人数がいますので、周りのカバー、フォローが行き届き欠員の影響をほとんど受けません。
そしてそうこうしている内に人員も補充され何の問題もなく以前のように回っていくことが可能です。
こういったパターンは比較的大病院に当てはまります。
やはり人数が多ければ多いほど一人抜ける影響は少なくて済みます。
欠員の影響度は医療事務員の数に反比例するという単純な話に落ち着くのです。
対してそんな単純な話にならないのが中小の病院です。
そもそも母数がそんなにいない中での一人の欠員はとてつもなく大きいのです。
そして今までかろうじてギリギリで回していたところがその状態におちいることは、ほぼアウトの状態を意味します。
そしてそんな状況の医事課って結構な割合であると思うのです。
それでも今現在そこの医事課がなんとかやっていけているのは現場の人が一生懸命頑張っているからにほかありません。
ひとが採れない
欠員が出れば当然人員を補充しなければなりません。
しかしこれがなかなか上手くいきません。
ここでもまたその病院での医事課のポジションというものが影響します。
結局のところ給与額設定の問題です。
ここはそれこそ病院によりけりですが、ご存じのとおり一般的に医療事務員の給与設定は結構な低さです。
他業種から見れば「そんな額で募集あるの?」っていう額だと思います。
根本的にここが一番の問題でありながら、経営陣が一番目をつむるところでもあります。
うちの病院はこの額なんだと、これ以上は上げられないんだと。
逆に言えば、その病院での医事課の評価は所詮その程度だということです。
現場目線で見るとホントに採る気があるの?って思ってしまうのです。
そしてある程度のレベルの人材を採ろうとすれば、そんな給与額設定のところにはいい人は来ないのです。
これは残念ながらそうなのです。
そもそも論として、医療事務は経験者が有利であるとか、優遇されるであるとかのたぐいの話はすべてウソです。
そんなものはありません。
その内容は以前に書きました。
 【転職】医療事務経験者が有利なんてウソです
【転職】医療事務経験者が有利なんてウソです
そしてある程度のレベルの人であるならば、それなりの待遇のところでないと応募すらしません。
その結果必然的にどうなるかといえば、それらの人の多くは給与水準が比較的高い大病院へと流れる、ということです。
そうです、そもそもそんなに欠員で困っていない大病院にさらに中小の病院が求めている人材は流れていってしまうということです。
第三者的な目線ですごく他人ごとのように書いていますが、当院も地方の中小病院です。
都会ならまだしも地方では本当に人が集まりません。
それも中小病院ならなおさらです。
それでもやっと応募があって面接まで進んだとしても、なかなか採用できる人が採れない。
応募の絶対数が少ないのでそこから選りすぐるということがかなり困難なのです。
そもそも事前にこちらが引いている最低ラインのレベルを超えてくる人が出てこない。
以前私はやっと応募があって面接まで進めてきた人を、ことごとく不採用にし続けるということをしたことがあります。
「逆にお前は採る気があるのか?」とそのとき上司に言われました。
私は別にそんな高いレベルの人材を求めているわけではありません。
未経験でも構わないし、年齢も問うてません。
でもそれでも採用できないわけは、将来的に戦力になり得ないと判断したからです。
私から言わせれば面接なんてそんなに難しいものではありません。
面接はゲームです。
自分をいかに高く評価してもらうか、その為の質疑応答の場に過ぎません。
 面接はゲームです【戦略とシミュレーションが大事】
面接はゲームです【戦略とシミュレーションが大事】
実際面接でその人の実力なんてわかるはずがありません。
極論すれば採用されるか、不採用かなんて面接官に気に入られたがどうかだけです。
だからぶっちゃけ上手くだましたもん勝ちなのです。
でもそれすらもできず、こちらがどういう人材を求めているのかも理解しないまま、ありのままの自分語りをするような人ではたとえ入職しても上手く立ち回れないだろうということなのです。
多くの人が誤解しているのは、募集側が求めているのは今までの実績がある人でも、過去の経験を大事にしている人でもありません。
欠員を埋めてあまりある、この先の戦力になる人なのです。
今まで積んできた経験はもちろん大事です。
ですがその学びさえも棄却して新たなことへ挑戦できる人こそが今後の医療事務員には必要です。
しかしながらそんな人にはなかなかめぐり会わないのです。
止まらない連鎖
ここで過去にうちの課で実際にあった超絶負の連鎖無限ループバージョンを紹介します。
ひとが辞める(マイナス1人)
→ひとが採れない
→欠員部分を一部の者でカバーする
→カバーしている者が疲弊する
→それを管理職がカバーする
→カバーしている管理職が疲弊する
→医事課全体が疲弊する
→もうムリと経験者が辞めていく
→さらにひとが減る
→依然としてひとが採れない(マイナス2人)
→欠員部分を残されたメンバ-でカバーする
→残されたメンバーがさらに疲弊する
→それを管理職がカバーする
→管理職がさらに疲弊する
→医事課全体がさらに疲弊する
→もうムリと残されたメンバーが辞めていく
→依然としてひとが採れない(マイナス3人)
→続く・・・
これはネタではなくて本当にあったできごとです。
今となってはひどい話だなというぐらいで済みますが、当時はかなりキツかったです。
そしてこの結末はある日を境に次々に採用が決まり、人も補充され徐々に業務も平常運転に戻っていった、ということになりました。
文章で書くとすごく単純に見えますが、そのある日というのはなかなか訪れず長くつらい底這いの日々が続きました。
ホント今となっては笑い話で済みますが。
教訓
今回なぜこの話を取り上げたかというと、このことからの教訓というのが人によっては真っ二つにわかれるということがわかったからです。
私がこのできごとから受けた教訓、感想というのは次のとおりです。
いくら目の前のことがきつくても、そこだけを見ていてはいけない。
そのはるか先を見すえた上で短期の解決を目指さず、中長期的な視点でのぞむことが大事。
底這いの日々だからこそ、いつかは上向く。
そのために今この瞬間に注力すべし。
私はこういう思考じゃないと苦難は乗り越えられないはずって思っていました。
ですがまったく正反対の意見が意外にマジョリティだということがわかって驚きました。
それは次のとおりです。
ひとが足りないと言い続けても、なんだかんだで仕事を回してしまうと「現場回ってるじゃん」って思われて終わり。
本気で上層部にどうにかしてほしいなら、仕事を回してはいけない。
決められた時間で帰って「回りませんでした」って言わない限り決して解決しない。
そういう状況で無理やり頑張る人って自分に酔っているだけ。
自分で自分の首を絞めるのはいいけど、周りの首まで絞めるんじゃねえ。
これはその人の置かれている立場でもいろいろと意見が分かれるところだと思います。
一担当者なのか、主任なのか、係長なのか、課長なのか、部長なのか。
しかしたとえ私が一担当者であったとしても後者の意見にはなりません。
あまりにも限界点が低すぎるんじゃないかって思ってしまいます。
以前にも書きましたができる前提とできない前提の差です。
 できると思えばできる【マインドセットの大切さ】
できると思えばできる【マインドセットの大切さ】
後者の意見は明らかにできない前提です。
できないなんて言えるのはホントにムリだとわかったその時点でいいのです。
そこまではできる前提の努力は続けるべきです。
そしてすごくそもそも論に立ち返るのですが、1人抜けたから1人補充する必要が本当にあるのか?ってことです。
まずそこから考える必要があります。
私は努力は肯定しますが、ただがむしゃらに頑張る努力ということに関しては否定的です。
努力には工夫が必要です。
頭を使って努力をしなければ高い生産性はのぞめません。
「回りませんでした」という人にはその視点が皆無のような気がするのです。
「回りませんでした」ありきの発想。
そこに至るまでに知恵は使ったのか、方法論を試したのか。
そして最も私が納得いかない点は、わかっていて回らない状況まで放っておいて、それで本当に良いのかってことです。
回りませんでしたとなったあとのことを真剣に考えていないだろうってことです。
回りませんでしたと言ったあとに辞めていく人ならまだわかるんです。
自分には関係ないことですから。
でも、そのあとも続けるのであれば、回りませんでしたの状態からの立て直しのときに自分はそこにいるわけです。
なぜわざわざ立て直しがめんどくさい一番の最悪状況までほっとくのか。
まだ、やれることはすべてやった、もうこれ以上はできません、っていう人ならわかります。
でもそんな人は決して「回りませんでした」とは言わない。
そんなところまで待たない。
後者の意見って一見とてもまともな意見に思えますが、実は単なる他責思考なだけなんじゃないかって思うのです。
 自責思考 VS 他責思考、 仕事での正解はどっちだ?
自責思考 VS 他責思考、 仕事での正解はどっちだ?
責任転嫁しているだけの行為。
「いやいや、他人が辞めることにどうして自分の責任が関わるんだ」って思う人もいるでしょう。
「勝手に同僚が辞めた尻ぬぐいをなぜ自分がしなければいけないんだ」と。
「自分の責任とは一切関係ないことなのに」と。
しかし本当にそうでしょうか?
自分には一切関係ないできごとに巻き込まれているのでしょうか。
たとえば突然辞めていく人。
これは自分には関係ないことですか。
なぜ突然辞めていくのでしょう。
これは明らかにお世話になった職場への敬意が一切ありません。
ということは所詮その程度の職場と思われていたってことです。
そしてそんな人って意外と多いです。
もちろんそのこと自体はその人自身の問題ですが、そう感じさせる職場の雰囲気作りにあなたも少しは影響を与えていたのです。
身から出たさびという言い方は厳しすぎるかもしれませんが、全然関係ないことはないのです。
突然辞めていく人がいる職場っていうのはそれなりにその内部に問題があります。
それを自分ごとと捉えられないようではあまりにも視野が狭すぎます。
メタ認知が効いていません。
何が言いたいのかというと「回りませんでした」という前にすること、考えることは山ほどあるだろってことです。
まとめ

ムリして回していたところが新たな標準点になるのはキツイ。
確かにそれはあるのかもしれません。
ですがこれも捉え方しだいで、そもそもの標準点がゆるかったんじゃないかともいえるわけです。
だってそれはムリしてとはなっていますが、人数を目安にしているだけでしょう。
もともとの人数が適正だったという根拠がない。
逆に多すぎたのが今回適正人数に落ち着いただけかもしれない。
ですがこれらはほとんどが主観であり感想なのです。
そこには検証がない。
過去から引き継いできた人工(ニンク)が正しいと思い込んでいる場合だって絶対あります。
あまりにも今までの常識、自分たちの常識に縛られている人が多すぎます。
そして挑戦もしなければ、失敗もしない。
その結果1ミリも成長しない。
そんな仕事の何が楽しい?
ホントにそう思います。
ひとが足らない場合には仕事を回すな?
本気でそう思っている人がいるなら言っておきます。
あなたにはひとが足りていても仕事を回す力などない。
他人のせいにしているんじゃねえ。
まずは自分で精一杯行動すること。
泣き言はそのあとでいい。
こんな考えはストイックなのですか?
マイノリティなのですか?
皆さんの意見もぜひお聞かせください。
 ごまお
ごまお