以前に「AI時代に医療事務員が生き残るために持つべき必須スキルとは?」という記事を書きました。
 AI時代に医療事務員が生き残るために持つべき必須スキルとは?
AI時代に医療事務員が生き残るために持つべき必須スキルとは?
そしてその中で必須スキルは問題解決能力ですと言いました。
今回はその問題解決能力を上げるためにはどうしたらいいの?という点について述べていきます。
目次
【ここがポイント】問題解決能力を上げるには何が必要?

結論
解けるか解けないかじゃない。
大事なのは「問題は解く前提」というマインド。
問題解決能力
問題解決能力とはトラブルや問題が発生したときになんとかする力です。
この力はあらゆる仕事で必要とされます。
特に今後の医療事務においては、この能力が高いか低いかで仕事の出来、不出来が決定するといっても過言ではありません。
今後の医療事務の行方というのは以前にいくつか記事にしました。
 【医事課長が解説】医療事務の将来性【10年後の世界とは?】
【医事課長が解説】医療事務の将来性【10年後の世界とは?】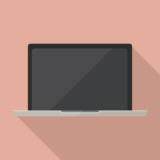 AIが支配?10年後に医療事務の仕事は残っているの?
AIが支配?10年後に医療事務の仕事は残っているの? 【医療事務】15年後には91%の仕事がなくなります【診療情報管理士】
【医療事務】15年後には91%の仕事がなくなります【診療情報管理士】
そこを要約すれば、医療事務という職業は将来的にAIに代替される部分とされない部分が出てくる。
される部分は計算化できる部分のすべてであり、されない部分はそれ以外、ということです。
そしてその計算化できない分野でのスキルが高いか低いかで医療事務員は評価されることになるということです。
そのスキルを具体的にいえば、ホスピタリティ、コミュニケーション、マネジメント、そして問題解決能力となります。
どれもが計算化は難しい分野です。
だったら将来的に医療事務の仕事はなくなりませんね、私たちも安泰ですね、と言いたいところですがそうはいかないのです。
なぜなら今以上にその分野のスキルが秀でていないと医療事務員としての価値はなくなってしまうからです。
たとえば、今ならホスピタリティやコミュニケーション能力がそれほど高くなくても、レセプトスキルが秀でている人であるならばその存在価値は十分高いです。
まさにレセプトで飯を食うというのがまだできるのが今の状況です。
そしてレセプトスキルが高い医事課と低い医事課では病院収益に明確な差がでます。
ICT化が進んできているとはいってもまだレセプト業務は人への依存度は高いです。
レセプトチェックの完全機械化にはまだまだほど遠く、人による目視点検が依然主流です。
そうなれば問われるのは個々の担当者のレセプトスキルです。
極端な話、まったくコミュニケーション能力もマネジメント能力もないが、レセプトの能力だけが異常に高いという人は今の時代であればそのポジションは安泰です。
そこにいてもらう価値は十分にありますから。
ですがそれは今のこの時代に限ります。
それこそあと10~15年後にはその人の評価はゼロに等しいことになります。
なぜならレセプトスキルがいらないからです。
コンピューターチェックをかけて終わり、そうなります。
そこには人が関わる部分が一切なくなる。
だからレセプトスキルという概念がなくなります。
もしくはレセプト情報を加工、分析するデータ処理スキルをレセプトスキルと呼んでいるのかもしれません。
どちらにせよ将来的にはレセプト業務は100%AIに代替される運命です。
であるなら、今後最重要視すべきなのは、ホスピタリティ、コミュニケーション、マネジメント、問題解決能力なのです。
しかしどれも一朝一夕に身につくスキルではありません。
多大な知識、経験の積み上げが必要になります。
ですがその中で問題解決能力だけは知識、経験の積み上げというよりは、マインドセットしだいでなんとかなる割合が比較的高いのではないか、そう思うのです。
問題は解く前提
このブログではやたらとメタ認知とマインドセットという言葉が出てきます。
それは「すべてはとらえ方しだい」という考えが私の中にあるからです。
そしてまさに問題解決能力はそこが肝なのです。
問題解決能力はその名のとおり能力であることには間違いないのですが、スキルというよりはマインドセットに大きく依存しています。
たしかに解決する能力はスキルそのものなので、知識や経験が必要になります。
ですがここで指すところはもっと前の段階です。
問題をどうとらえるかという部分なのです。
ここがその人自身のマインドセットが大きく影響するところなのです。
そしてここで大事になるのが、問題は解く前提という姿勢です。
そもそもここがないと問題解決能力を上げることなど絶対ムリ。
なぜなら問題を問題としない限り解決能力は養われないからです。
そりゃそうです。
問題が起こらないのに解決能力だけが上がるなんてことはないのです。
だから問題が起こらないと何も始まらない。
ですが、その問題自体を起きないように頑張る人というのが一定数います。
これは潜在的な問題に対して事前にアプローチし、問題が顕在化する前に解決しているというような積極的介入の話ではありません。
実際そんな例はほとんどありません。
ここでいう問題を起きないようにするというのは、たとえば話を詰めていけば間違いなく意見がぶつかる問題だからひたすら先延ばしをするだとかいうたぐいのものです。
つまり、問題は起きないが成果も上がらない。
結果、何も良くなっていないし、火種はそのまま残っている、という状態です。
これではただの事なかれ主義です。
この人のマインドセットは間違っているのです。
そもそも問題が起こるのは前提。
そしてその問題は解く前提でいなくてはいけない。
私たち医療事務員は問題を解決するために存在している。
受付、計算、会計、レセプト作成 etc・・・。
ただそれらのルーチンワークを粛々と行い、作業をし続けることで私たちは給料をもらっているわけではないのです。
そしてまたそれらの業務をきちんとこなすことで仕事での評価が上がるわけでもないのです。
ルーチンワークはあくまでルーチンワークでしかない。
そこには付加価値がつかない。
そしてそれでは人がやっている意味がない。
ルーチンワークで給料がもらえているともし思っているのであれば、あなたはAIへの代替候補1番手です。
だってそれならロボットと何ら変わりないから。
人間がやる意味がないのです。
人間をそこに置く意味は、人間は問題解決能力があるからです。
問題を解決できるからこそ、その対価として給料は支払われているのです。
であるならば問題を先送りにしている場合ではないのです。
問題をなかったこととしてもみ消している場合ではないのです。
問題はどんどん見つけるべきなのです。
そしてどんどん解いていくべきなのです。
医事課というところは日々何かしら問題が起きます。
トラブルも大小さまざまいろいろ発生します。
ですがそもそも「問題は解く前提」というマインドセットであるならば、臆することなど何もないのです。
むしろ「よしキタ!」「さっそく解決に向かおう」と思えるのです。
そしてそれを繰り返していれば問題、トラブルがそんな大変なこととも思わなくなるのです。
だって解く前提ですから。
それは自分が必要とされているという証拠なんですから。
そして解く前提なので解けないとは決して考えないのです。
解けると思ってその問題に向き合っている。
結局問題解決能力を上げるためには、その前段階で問題は解く前提というマインドセットをしっかり作っておく必要があるのです。
これはスキルというよりかは心構えです。
そう思えるかどうかなのです。
結局「できると思えばできる」というところに帰結するのです。
 できると思えばできる【マインドセットの大切さ】
できると思えばできる【マインドセットの大切さ】
まとめ

そもそも問題解決には
・問題の発見
・原因の分析
・解決策の思考
・解決策の実行
・振り返り、フィードバック
という一連の流れがあります。
しかし今回の記事ではその部分は一切ふれていません。
どうしてかというと、その部分はある意味訓練だからです。
繰り返し行うことでその部分の能力は上げていくことはできます。
ですがそもそもその土台となるマインドセットが構築できていなければ、その問題解決フェーズに入ることさえできないのです。
いつまでたっても問題にぶつからない、向き合えない。
それだと訓練にさえならない。
大事なのは問題を問題としてとらえられるマインド、問題は解く前提というマインド。
スキル論というよりマインド論です。
ですがここが一番重要なのです。
アイスバーグ理論のとおり、技術論を語る前にとにもかくにもマインドセットなのです。
 「自分には医療事務しかない」なんて思わない方がいい【成長マインドセットとアイス バーグ理論】
「自分には医療事務しかない」なんて思わない方がいい【成長マインドセットとアイス バーグ理論】
ここを整えておかなければ良い仕事なんかできない。
問題解決能力を上げるために一番必要なものとは、困難は避けるものではなく、乗り越えるものととらえられるマインドセットなのです。
 ごまお
ごまお


