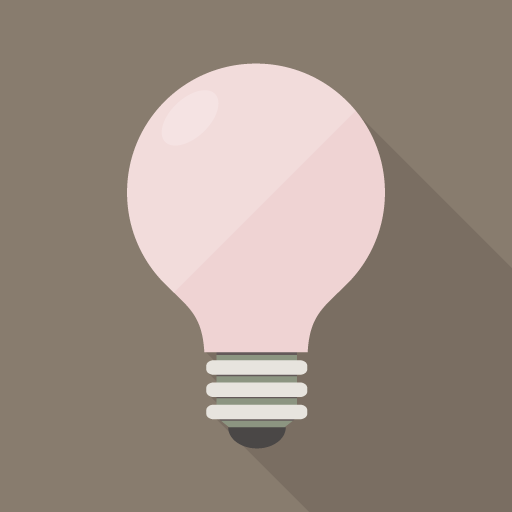一般的に高学歴の人は頭がいいと言われます。
そして頭がいい人は仕事ができるはずだと誰もが思っています。
ですが高学歴なのに仕事ができない人は確実にいます。
大卒で仕事ができない人がいる一方でかたや高卒でめちゃめちゃできる人もいます。
この差はどこで生じるのか。
今回はこの点を深堀りします。
目次
勉強はできるのに仕事ができない人に足りないものとは?

結論
足りないものはメタ認知力です。
勉強と仕事
頭がいい
一般的に勉強ができる=高学歴=頭がいいとされます。
そして頭がいい人は仕事ができるというイメージを僕たちは持っています。
ですがそもそも頭がいいという表現があいまいです。
そしていわゆる高学歴が指している頭の良さというのは記憶力がいいということです。
日本の大学入試は完全なる暗記の勝負です。
暗記するための根気がありコツコツ努力できる人が入試に受かるようになっています。
すべてがそうだとはいいませんが傾向としてはそうです。
つまり知識量の問題になります。
ですのでそこには創造力や発想力はほぼ必要とされていません。
そしてそのような勉強ばかりしていると与えられた課題を解くことは得意でも、0から1を生み出す能力が全然育ちません。
しかし社会に出ると教科書どおりの答えなどありません。
入試でつちかわれた頭の良さでは通用しない理由の1つがそこにあります。
勉強はできた方がいい
前述のとおり入試でつちかわれた頭の良さは社会では通用しない、というのはそのとおりです。
ですがだからといって、勉強と仕事はイコールではないとも思いません。
そもそも大部分の勉強ができて高学歴の人は、勉強ができない人よりは優秀です。
これは当然の話で物事を論理的に考える能力、目標に向かって計画的に取り組める能力、諦めずに続ける粘り強さなどが普通の人より優れているから高学歴なのです。
そしてこれらは仕事をする上でもとても大事な要素です。
ですのでやはり勉強はできた方が仕事上も有利なのです。
求められている能力が別
知識をインプットするいわゆる勉強と呼ばれているものは、上記で述べたようにできるに越したことはありません。
ただし、だから仕事につながるか?仕事ができるようになるか?といえばそれは別問題です。
いわゆる勉強というものは、答えがあるものを効率よく間違わないでやることです。
ですが仕事は答えのないものの問題点を見つけて解決策を見いだすものです。
つまり0から1を生み出す能力が必要です。
この2つは求められている能力がまったく別なのです。
仕事と能力
仕事に求められる能力とは?
ひとことでいえばメタ認知力(俯瞰力)です。
つまり自分の仕事、役割を客観的に見る力です。
以下に仕事ができる人の共通点をあげました。
・仕事の全体像を把握できる
・物事を多面的にとらえられる
・思考に柔軟性がある
・決まったやり方に固執しない
・周りのやり方を参考にしたり耳を傾ける
・試行錯誤を惜しまない
・感情のコントロールがうまい
これらに該当する人は間違いなくメタ認知力が高いです。
逆にいえばメタ認知力が高ければ仕事ができる人により近づくということです。
勉強ができる人のおちいりがちなことの1つに完璧を目指してしまう、というのがあります。
知識や勉強が重要だと考えている人ほど仕事を完璧にこなしたい、課題を完全に解決しないといけないと考えが強いです。
ですが仕事に完璧なんてありません。
そして仕事には期限があります。
完璧なんか目指すよりとっとと終わらせる方が先決なのです。
 完璧を目指すよりまず終わらせろ【医事課の仕事は完了主義】
完璧を目指すよりまず終わらせろ【医事課の仕事は完了主義】
ですがメタ認知力が低ければそんなことには気が回りません。
目の前のことがすべてで仕事は自分で頑張るものだとだけ思っています。
そもそも完璧かそうでないかは自分で決めるものではないです。
他者が判断するものです。
自分で完璧と思っているのであればそれはひとりよがりなだけです。
まずは完璧なんか目指すよりはとりあえず終わらせること。
そして自分は組織の中の1人という意識をなくしてはいけません。
医事課でいると特にこの部分が感じにくい場面があります。
たとえば入院係です。
入院係は1つのチームですが、担当者はその意識はあまり強く持っていません。
なぜなら基本的に自分が担当している病棟や診療科の業務をきちんとこなしていれば何も問題ないからです。
また自賠責担当や労災担当、健診担当なども同様です。
それぞれが担当分をきちんとこなしていれば何も問題はありません。
ですがそれではいつまでたっても0から1を生み出すことは不可能です。
決まった答えのない中で試行錯誤して模索して業務改善を行っていく。
それによって医事課最大のミッションである病院収益の最大化につなげていくことが大切なのです。
そのためには医事課が1つのチームとして同じ方向に向かう必要があります。
そのときに自分の担当業務とその役割を客観的に見て、医事課に貢献できる仕事のやり方を考えなければいけません。
それにはメタ認知力の向上がマストなのです。
知恵と行動
フランスの哲学者パスカルの言葉に「知恵は知識にまさる」というのがあります。
知識は必要ですが知識だけでは良い仕事をすることはできません。
そこには柔軟な思考でものごとを多面的にとらえ、人の意見に耳を傾け、臨機応変に対応するスキルが必要です。
そこに知恵が生まれます。
それこそがまさにメタ認知力なのです。
そしてそのメタ認知力を活かすためにはアウトプットが必要です。
これからの時代は何が本当の答えかはっきりわからない時代です。
自分の力で考えて、自分で答えを出して、それを自分で実行することをやっていかないといけない時代です。
医療の世界を見てみればこの先はまさにカオスの時代です。
今後経験したことのない超高齢化社会がやってきます。
予測できないようなAI・ICT時代に突入します。
そこに決まった答えはありません。
勤務先が医療機関だからといって安定しているとは限りません。
決められたとおりの保険請求をしていれば安定的に収入が得られるなんてこともありません。
もう固定化された方法なんてないのです。
だから今まで引き継いできた業務のやり方も正解かどうかなんてわかりません。
そこを考え試行錯誤するという知恵と行動が絶対必要なのです。
まとめ

勉強はできるのに仕事ができない人って一定数いると思います。
このことについて書いてある記事はググればたくさん出てきます。
それほど世の仕事をしている人の中での共通の認識なんだと思います。
ですが実際の割合ってどれくらいなのでしょうか?
これは結構バイアスがかかった記事や結論ありきの記事が多いように見受けられます。
つまり、勉強ができるというのと仕事ができないというギャップに注目させ「そうだよね。いるいるそんな人」という共感を持たせる記事構成にしているということです。
何が言いたいのかというと、「勉強はできるのに仕事ができない人」は確かにいますが実際は「勉強ができて仕事もできる人」が大部分なんじゃないかということです。
だから余計に「勉強はできるのに仕事ができない人」が目立ってくるのです。
結局勉強ができようが、できまいがそんなことは関係ありません。
仕事ができる人というのはメタ認知力が高い人です。
仕事を俯瞰して見れる人です。
そしてそれは決して先天的な能力ではありません。
時間はかかりますが誰にでも上げていくことはできます。
またそれは自分を必ず助けてくれます。
メタ認知力の高い医療事務員はできる医療事務員です。
これは間違いありません。