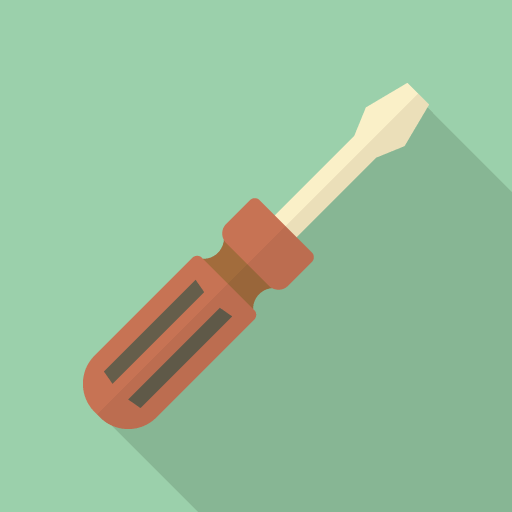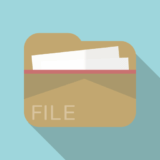先日「医療事務スペシャリストになる方法」という記事を書きました。
 【まるっと解説】医療事務スペシャリストになる方法
【まるっと解説】医療事務スペシャリストになる方法
しかし今日の主張は「医療事務のスペシャリストなんかいらない」です。
これは完全に矛盾しているように受け取られてしまうでしょう。
ですが矛盾はしていません。
主旨としては、ある条件を満たすような医療事務スペシャリストは不要だ、という内容です。
つまり分業制によって作られるスペシャリストのデメリットを認識しておこうということです。
分業制のデメリットを認識してもらうことによって、今後の業務運営に役立ててもらえるはずです。
目次
医療事務のスペシャリストなんかいらない【分業制のデメリットとは?】

結論
分業制は必要ですが、大切なのはバランスです。
なにより仕事を俯瞰して見れる目が必要です。
分業制
業務分担
どこの医事課でもみんなでローテーションして行っている業務もあれば、特定の担当者に任せている業務もあります。
経験が浅くてもなんとかやっていける受付業務や保険証確認、入力業務はローテーションでも可能です。
対して保険請求、公費、労災、自賠責などある程度の経験や知識が必要な業務は、分業制にした方が効率的に業務を回せます。
業務の効率化と事務員の専門性の向上を考えれば、分業制は当然とるべき手法の1つとなります。
メリットとデメリット
ここで分業制のメリットとデメリットを見ておきましょう。
まずメリットですが、これは業務の効率化です。
そして専門性に集中、特化することによってその分野のスペシャリストに育成できます。
反対にデメリットですが担当者でしか対応できないことや、客観的なチェック、評価ができないことが挙げられます。
そして1番のデメリットが自分の業務にしか目がいかなくなる、興味がわかなくなるということ。
つまり医事課の業務を俯瞰して見られなくなってしまうということです。
たった1人はダメ
今述べたように分業制にはメリット、デメリットの両方があります。
結論から言ってしまえば、大事なのは分業具合のバランスです。
あまりにも専門性に特化した分業では、デメリットの方が大きくなります。
そしてもう1点大事な点は、複数人で担当すべしということです。
最低でも2人は必要です。
中小の医療機関ではマンパワーの問題で、どうしても1人担当となってしまう業務があります。
しかしこれはかなり危うい状況です。
まずよくありがちなことが担当者不在時の対応ができない、ということです。
たとえば事故請求において普段なかなか連絡が取れない患者から電話がかかってきたのに、その日に限って担当者が休みという場合があります。
この場合1人担当だと、もうこの時点で対応できません。
後日もう1度連絡を取り直す必要があります。
これは非常にロスのある業務のやり方です。
しかし2人いればこんなことは起きません。
そしてこれよりもっと危ういのが、他の事務員によるチェック機能が働きにくくなる点です。
つまりその人しかわからない業務というのが、発生してくるということです。
そうなると周りから見ても正しいのか、間違っているのかの評価がとても難しくなります。
これは業務の中身についてもそうですし、それに投下している時間が適正なのかどうかの評価もできません。
言ってしまえば1人担当者のさじ加減ひとつな業務になってしまう、ということです。
これは非常に危うい状況です。
その担当者がどんな大ベテランで仕事も完璧にこなすという人であっても、それだけは絶対避けないといけません。
基本的に人はミスを犯すもの、自分には甘いものということを前提にしておくことが必要です。
であるならば分業制といえども、最低は2人以上のチームでの分業制とすべきなのです。
マインド
一般的に医療事務のスペシャリストといえば、その業務に対するスキルを指します。
これはもちろん高いに越したことはありません。
どんどん知識、経験のスペシャリスト化を目指してもらえばいいことです。
ですがここでそのスペシャリスト化による副作用が出てくる場合があります。
それがマインドのスペシャリスト化です。
医事課において明確に役割を分担し、その分野のスペシャリストを育成するのは間違ってはいません。
ですがここできちんと認識しておかなければならないことがあります。
それは明確な役割分担が行われることと、医事課としてのベストなアウトプットを出すことはイコールではない、ということです。
簡単にいえば医事課はチームなのだということです。
大事なことは誰の為に、何の為に働いているのかということです。
そこは第一には患者のためです。
だとすれば自分が担当している業務以外は一切関わらない、やらない、協力しないというスタンスではその目的とズレてくるのです。
つまりそれらはすべて、患者の利益に逆行していることになるということです。
ですが本人からするとそうは思わないのです。
なぜならスペシャリストという自負があるからです。
分業意識があまりに強いため自分のアウトプットにしか注目しなくなり、医事課の成果という視点が抜け落ちてしまうのです。
ようやくここでタイトル回収をしておきます。
「医療事務のスペシャリストなんかいらない」というのは、チーム意識のないスペシャリストはいらないということです。
どんなにその個人の能力が高いものであったとしても、個人プレーに徹する医療事務員はいりません。
結局それは自分のためだけに働いているだけです。
たとえ分業制であったとしても、自分はチームの一員なんだという意識がどんな場合においても必要です。
それがあれば周りと積極的にコミュニケーションをとり、医事課全体を見渡せる広い視野を持つことも可能です。
ひいてはそれが自分個人のアウトプットのクオリティを高めることにもつながります。
そのことをわかっていない、またはわかろうとしない医療事務のスペシャリストなんかいらない、ということです。
まとめ

分業制にはメリット、デメリット両方あります。
大切なのはそのバランスです。
そして仕事に対するマインドです。
それは部署全体を俯瞰して見ることができるマインドです。
一歩引いて自分を含めた医事課全体を見渡せる目、ということです。
しかしこれを行うことは、実際かなり難しいです。
そのような仕事の仕方は、ある程度経験を積まないと無理と思えるかもしれません。
ですがある程度経験を積んでも、その意識を持てない人はいつまで経ってもできません。
ですのでそれは経験の差ではありません。
仕事への向き合い方の問題です。
目先のことにしか気が回らない人にとって同僚を助ける、フォローするという行為は自分にとって何の得にもならないと思うかもしれません。
それよりも自分の専門分野に注力することの方が、よっぽど大事で病院の役にも立っていると思うかもしれません。
ですがそれは違います。
病院の役に立つということは、前提として患者の役に立っていなければいけません。
だったら「担当者が不在で対応できません、わかりません」ではダメなのです。
そうではなくて「担当者は不在ですが私が対応できます、わかります」の方が100倍患者の役に立っています。
そのためには自分には何ができるのか、どうしていけばいいのかをつねに考えられるスペシャリストこそが医事課でいう本当のスペシャリストです。
つまり専門分野に特化しつつもチームのことを考え行動できる人こそが、真の医療事務スペシャリストなのです。
周りのことを考えられる医療事務スペシャリストに、ぜひなりたいものですね。