ひとことで医療事務といってもその中でいろんなセクションに分かれます。
一般的に医療事務という場合には受付、計算、会計、レセプト業務を行う担当者を指すことが多いです。
ですがそのほかにも、診療情報管理士や医師事務作業補助者といった職種も医療事務のくくりです。
医療事務の未来はなかなかに厳しいと過去に書いてきましたが、その医療事務とは一般的に考えられている医療事務を指しています。
ですので診療情報管理士や医師事務作業補助者などは、また違った側面からの検証というものが必要になります。
ということで今回は医師事務作業補助者を取り上げます。
「医師事務作業補助者の未来ってどうなの?」「将来性はあるの?」と悩んでいる現職の方はもちろん、今後医療事務業界に入ろうとしている方はぜひ最後までお読みください。
将来を考える上できっと何らかのヒントが得られるはずです。
目次
医師事務作業補助者の未来ってどうなの?【DC・MAの存在価値】
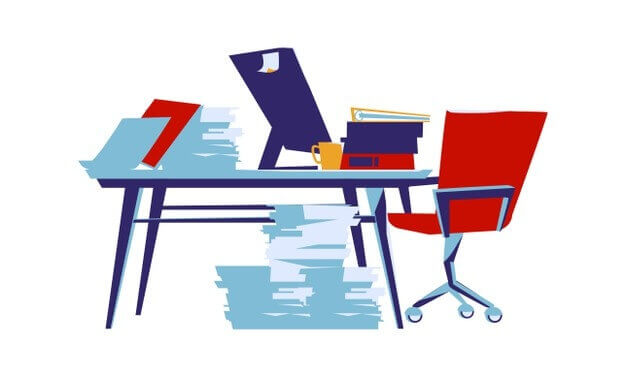
結論
存在価値はより高まっていきます。
将来有望な職種に育つ可能性は十分にあります。
医師事務作業補助者について
医師事務作業補助者とは
まず医師事務作業補助者とはどんな職種なのかを説明します。
医師事務作業保持者は医師の業務負担を軽減するために、医師が行う幅広い業務内容のうち事務作業をサポートする人のことです。
病院によって様々な呼称があり医師事務作業補助者のほかに
ドクターズクラーク(DC)、メディカルアシスタント(MA)、メディカルセクレタリー(MS)、医療秘書
などと呼ばれています。
業務内容
医師事務作業補助者の業務は医師の指示の下に
診断書などの文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業、並びに行政上の業務への対応
に限定するとされています。
そして、医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求業務、窓口・受付業務、医療機関の経営、運営の為のデータ収集業務、看護業務の補助並びに物品運搬業務等については業務としないとされています。
診療報酬改定
2018年改定により
多職種からなる役割分担推進の為の委員会又は会議を設置し、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を作成すること等
が施設基準要件とされるとともに点数の引き上げが行われました。
このことからも分かる通り、厚生労働省は働き方改革のもと医師の負担軽減に躍起になっており、まただからこそ当加算を依然高く評価していることがわかります。
この流れは次期改定においても引き継がれるものと思われます。
医師事務作業補助者と診療報酬
政策上の必然性
現在の診療報酬において高い点数を算定しようと思えば、どうしても病床回転率を高めざるを得ない報酬体系になっています。
そうなると必然的に全体の流れが早まり、医師の仕事もより忙しくなっていきます。
そのような背景で医師事務作業補助者の役目は、医師の業務効率化を行い病院の労働生産性向上を成し得るためにさらなる寄与を果たしていくことです。
国の政策誘導をたどっていくと、医師事務作業補助者はさらに必要性が増してくるというのは必然なのです。
点数
医師事務作業補助体制加算の点数は改定ごとに上がってきており、導入期から成長期、そして成熟期へと右肩上がりに進んでいます。
医師事務作業補助者の機会損失コスト
機会損失という考え方があります。
これは発生した損失ではなく最善の意志決定をしないことによって、より多くの利益を得る機会を逃すことで生じる損失のことをいいます。
ですので本来時給の高い医師が代替性のある事務作業を行うことは、多大な機会損失コストが発生しているのです。
例えば、3,000円の診断書を1時間で4枚作成すると12,000円となります。
同じ1時間でも上部内視鏡検査を1時間で2件行うと11,400円×2=22,800円となります。
この場合10,800円が機会損失コストをなります。
医師には本来どちらをやってもらう必要があるのかということです。
代替性のある事務作業なら医師自ら行うことよりも、そこを医師事務作業補助者が行うことにより医師が診療に専念することで収益増が生まれるのです。
この機会損失コストというのは、かなり多くの場面で発生しています。
さらに医師と医師事務作業補助者の時給の違いを見れば、診断書作成の利益率も大きく異なります。
トータルで見てどれが医師にして貰うべき業務なのか、どれを医師事務作業補助者にして貰うべき業務なのかを見極めることが大切です。
医師事務作業補助者とチーム医療
チーム医療では代替性という考え方が重要です。
現場の忙しい仕事の全部が、国家資格保持者でないと出来ない業務なのかということを考えることが必要です。
そして労働生産性が上がる国家資格保持者でしかできない業務へ専念させ、それをまわりで支えるのがチーム医療です。
医師事務作業補助者の存在価値
地域にとって必要な病院はなくなりません。
存在価値があれば需要があり残り続けます。
同じように医師事務作業補助者も病院にとって存在価値を示せば残り続けます。
むしろより高い評価をされていく可能性もあります。
時代の流れ、医療政策の今後を思えばますますその存在価値は高くなっていくと思われます。
しかしそのためには医師事務作業補助者自身の自己研鑽、レベルアップというものが必要不可欠です。
実際現場では人材の資質の幅に大きくばらつきがある、定着しない、思ったような活用ができていないなどの課題があることも事実です。
これらの原因には専門的な教育システムの未整備や業務内容、業務範囲の不明確さなどがある場合も見受けられます。
実際医師事務作業補助の職に就いてみたものの、現場のレベルについていけず辞めてします人も少なからずいます。
今後の将来性は有望なもののそれなりの能力、専門性が要求される職種なので生半可な気持ちで志すのだけはやめたほうがいいです。
できれば診療情報管理士などの資格などを目指すぐらいのモチベーションがあれば、よりよいキャリアアップに繋げていけるのではないかと思います。
これはあくまで例であって資格はなくてもいいですが、つねに学ぶ姿勢だけは忘れないでほしいと思いますし、そうでないと今後求められる医師事務作業補助者像には近づいていきません。
まとめ

医師の働き方改革は国の喫緊の課題であり、その解決のためには医師事務作業補助者の活用はマストであるというのが現状の診療報酬制度の答えです。
この方針にさらに加速し、次回以降の改定においても医師事務作業補助体制加算については追い風となっている可能性が非常に高いです。
そして機会損失コストを勘案した上で、その需要がより高まっていくというのは無理な推論でもありません。
将来的には現行の任意の加算ではなくて、看護職員配置と同様に施設基準で入院患者○人に医師事務作業補助者1人のように規定される可能性だってゼロではありません。
そうなった時に問われるのは、やはり医療の質という1点です。
ただ数が多ければいいということではない、どれだけ病院にとってかけがえのない存在となるか、医師の業務の効率化に寄与できるか、求められることは非常に高いレベルにあります。
それに応えられるだけの人材が、数多く生まれることを心から願っております。
そして医事課と共に同じ事務職として医療を裏から支える屋台骨として機能できるように、お互い切磋琢磨していけたなら素晴らしいことです。


