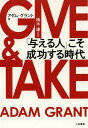先日こんなツイートをしました。
ムカつく上司からでもその人を反面教師にすれば、どう人と接するべきかを学べる。できない部下からでも自分の教え方の悪かった点を学べる。どれだけ経験を積んでも人から教わることはつねにある。大事なのは素直さと謙虚さ。それがある人は必ず伸びる✨#デイトラ#駆け出しエンジニアと繋がりたい
— トシ@医事課の思考 (@ijika_no) May 10, 2020
私はいつもこう思っています。
ムカつくあの上司だって反面教師にしちゃえば、たちまち役立つ上司に早変わりです。
今回は反面教師は最高というテーマで述べていきます。
目次
【仕事のキホン】反面教師は最高の教師!

結論
ムカつくな、戦うな、学びとれ。
良い上司なんていない
そもそもなんですが部下から見て良い上司なんて存在しません。
というか良い上司、悪い上司というような二元論的な区分けはできないのです。
良い上司にも悪い面はあり、逆に悪い上司にも良い面は必ずあります。
ですのでこの人は良い上司だって思っているのは良い面だけが強調されてあなたに記憶されているに過ぎないのです。
まあそれが良い上司の定義なんだと言われればそれまでですが。
話を戻しますが、部下から見て良い上司がいないのは当たり前なのです。
なぜならお互いはかみ合っていないからです。
もっとわかりやすく言えば、俯瞰度が違うのです。
見ている視野の広さが違う。
見ている方向が違う。
部下は足もとを見ているのに上司ははるか先を見ている。
お互いがかみ合わないのは当然です。
目指すべきゴールの認識が違うのだから100%意思疎通できるはずがないのです。
ですので上司は部下に対して「言われたとおり従え」と思い、部下は上司に対して「あんた何にもわかってねえ」と思うわけです。
これはどちらもが抱く自然な感情なのです。
そして今後もこの図式は変わりようがないのです。
ムカつくから無能
これは私の推測なのですが、世間には有能と思われている上司よりも無能判定されている上司の方がはるかに多いと思います。
私もその1人かもしれませんが。
でもこれは先ほども言ったように当たり前の話なのです。
評価する部下とその上司が同じライン上にいないのですから。
当然ながら部下は部下目線でしか上司を見ません。
そこでもし仮に、上司の立場にも立って、上司、部下両方の視点でものごとを見ることができる部下がいるのであれば、その人はもはや部下の位置にはいないでしょう。
まずそんな部下はいないのです。
「自分はこんなに頑張っているのになぜ認めてくれない?」
「もっと私を評価しろ」
「現状もよく知らないくせに仕事ばっか振ってくんじゃねえ」
だいたいはそう思います。
というか私はそう思っていました。
そのときの私は直属の上司に対してホントに幻滅していました。
腹立つとかムカつくとかじゃないんです。
幻滅です。
いうなれば無力感です。
「この人には何を言ってもムダ」
「自分の出世のためだけに部下がいると思ってんじゃないの?」
「知りもしないくせにいちいち口出してくんじゃねえ」
いつもそう思っていました。
その結果その上司を「無能」とラベリングしていたのでした。
しかしホントにその上司が無能だったのかと言えばそうではないはずです。
前述したとおり「良い」「悪い」「有能」「無能」の二元論では区分けできないのです。
間違いなく有能な部分はあるはずなんです。
でないと上司になっていない。
上司のその上司からこの人優秀と評価されているからこそ上司という立場なのです。
ただその優秀さは部下にはわからないという話です。
私の場合もその優秀な部分はまったくわからずじまいでした。
しかし普通に考えれば優秀さはわからなくても、無能まで一気に評価が落ちることはありません。
優秀じゃない上司は無能なのかといえばそうではないのです。
だったらなぜこれほどまでに世間では無能判定される上司が多いのか?
その答えは部下のバイアスがかかっているからです。
「上司が無能だからムカつく」ではなくて「上司がムカつくから無能」なのです。
数々のボタンの掛け違え、コミュニケーション不足などから蓄積された部下のうっぷんがどこかの段階で「ムカつく」に変わります。
そしてそのムカつく感情を正当化するためにもう無能と決めつけるのです。
そして少しでも有能ぽいことがあったとしても、もうそれはできて当然のこととして片づけてしまう。
だから極端にいえば、もう何をしたところで、何の結果を出したところで無能はくつがえらないのです。
無能な上司にムカつくのって当たり前でしょってことです。
だからバイアスは怖いのです。
そしてまたバイアスがかかっていることに気づけないということが一番怖いところなのです。
「ウチの上司は無能」って思っている人は、もうそういう見方しかできないということが悲しき現実なのです。
敵に見えるのは戦おうとしているから
本来上司は味方です。
同じ医事課の仲間なのですからそりゃ当然です。
しかしムカつく上司の場合、それは一転して敵になります。
上司なのに敵。
これは一番やっかいです。
どうしようもない無力感、ただただ無力感。
もっと悲壮感を出す表現をすれば絶望です。
当然です、敵が上司なのですから。
どう見ても自己中、どう見てもナルシスト、どう見てもテイカー。
(※アダム・グランド著「GIVE&TAKE」によると、人はギバー、テイカー、マッチャーの3つにわかれる)
部下から見れば敵以外のなにものでもないです。
そしてそんな部下の敵対心オーラは上司にも伝わります。
その結果余計に上司からの心証は悪くなり一層の敵となる。
これは完全に昔の私です。
でも今にして思えばこれは損な立ち回り方なのです。
だって戦っても勝てませんから。
パワーバランスは逆転しませんから。
やるべきことは批判なのではなくて学びなのです。
私がその上司が敵に見えていたのは戦おうとしていたからでした。
欠けていたのは学ぶ心です。
反面教師というマインドが完全になかったのです。
反面教師マインドのハードル
反面教師に似たようなことわざで「人のふり見て我がふり直せ」というのもあります。
このどちらも誰もが知っていることばですが、言うは易く行うは難しとはこのことで、これを実行するのはなかなか難しいです。
なぜならこれらは結局メタ認知力が必要だからです。
「他人のやっている動作や態度で好ましくないと感じたら、その相手をとがめる前に、自分は他人に対して同じようなことをしていないか、他人の行動を自分ごととして見つめなければならない。」
これをわかっていることと、行動できることはまったく別物です。
行動できる人はそんなに多くはない。
それほど悪い見本から学ぶって行為はハードルが高いのです。
そこでは間違いなく自分の感情が邪魔をするからです。
相手の行動の事象と自分の感情とは完全に分離しておく必要があります。
そのためにはメタ認知力が絶対必要なのです。
やはり最強スキルはメタ認知なのです。
 【スキルは身を助ける】最強スキルはメタ認知!
【スキルは身を助ける】最強スキルはメタ認知!
反面教師の副産物
反面教師はその人の悪い面を見て、自分をかえりみ、自分ごととして落とし込むことによって、己の血肉にできるという効果があります。
反面教師の人物が犯す誤りは、人々に正しい自覚をうながす貴重な教材となります。
ですので反面教師ってとてもありがたい存在なのです。
そしてまたその副産物がすばらしい。
反面教師というのを意識すると、腹立つ人、ムカつく人が一切いなくなります。
だってみんな私の先生だから。
どういう言動が相手を不快にさせるのか。
どういうもの言いが相手のモチベを下げるのか。
自分自身では気づきにくいことを身をもって教えてくれます。
悪い見本として実演してくれるのです。
こんなありがたい教材はありません。
しかも無料。
だったらフルに利用すればいいのです。
たとえトンデモ発言をするクソ上司であっても
「そういう発想しますか」
「へぇー斬新だなあ」
「この人のアタマの中、どうなっているんだろう」
という見方ができれば、ムカつくことなく上司とつきあえます。
この状態はもはや仲間でも敵でもなく、完全なる第三者なのです。
こうなればしめたもので、対人関係のストレスというのは確実に減っていきます。
人ってどうしたって自分と合う人、合わない人というのはあります。
それは間違いない。
だったら合わない人を避けられるのか。
仕事ではそれはムリです。
それが自分の上司だったらなおさらムリ。
だったらどうすべきか?
反面教師+第三者視点。
これで最強です。
学べてストレスが減っていく。
この最強メソッドを使わずして何を最強と言えるでしょうか。
まとめ

どんな人からでも学びは得られる。
ホントにそう思っていればそうできます。
大事なのはその前提のマインドセットがあるかどうか。
最後にひとつ大切なポイントを伝えておきます。
イヤな思いをしたら「勉強になりました、学べました、ありがとう」と感謝してみてください。
「なんでイヤな思いしてるのに感謝せなあかんねん」と思っている人、それはイヤな思いだからです。
その瞬間あなたは反面教師から教わったのです。
教えてもらったらお礼をいうのが礼儀でしょ。
反面教師は最高の教師であるというマインドセットを持つことで、今日からのあなたの仕事ぶりは変わるはずです。
ぜひ変えてみてください。
 ごまお
ごまお