医療事務の資格には国家資格はありません。
全て民間資格です。
そしてその数はかなり多く数十種類に渡ります。
その中でも最難関と言われている診療報酬請求事務能力認定試験という資格ですが、
はたして取得しておくべきなのか否か、ということにフォーカスします。
 ごまお
ごまお
目次
診療報酬請求事務能力認定試験の資格は必要か?
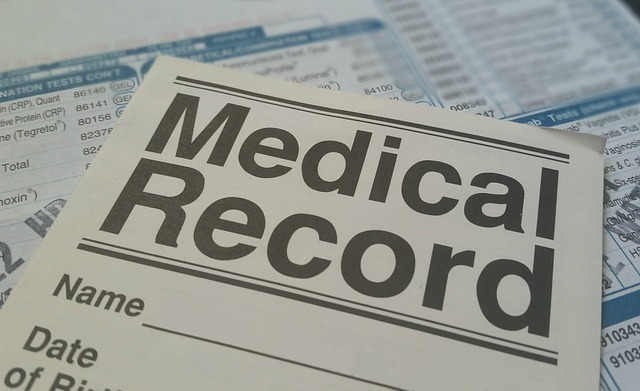
結論
必要はありません。
前提として
そもそも何に対して必要か必要でないかの判断を下しているのかを明確にしておきます。
私の場合は単純に費用対効果のみで判断しています。
すなわち投下したコスト、時間、労力に見合うリターンがあるかないかということです。
医療事務資格いる、いらない問題ではえてしてこの判断基準が漠然としたままで論議されてしまいがちです。
時間もお金も関係なく資格取得を語るのならば新しい知識を身につける行為を不必要とは誰も言いません。
ですがとったからといって何の恩恵もない資格に時間を費やすことはほんとに意味がないのです。
医療事務の資格にはそのようなものがごまんとあります。
ネットでは医療事務として働く為に役立つ資格として診療報酬請求事務能力認定試験や医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)、医療事務管理士をはじめありとあらゆる資格を見つけることが出来ますが、すべていらないです。
例えば面接時にそのような資格があるからといって有利に働くことはまずありません。
同じ年齢、同じ能力の2人の中から1人を選ばないといけないという場合になら有資格者を選ぶとは思いますが所詮その程度のものなのです。
ですがそういう私でも資格取得の意味があるかもしれないとかろうじて思えるのはこの診療報酬請求事務能力認定試験だけです。
これはどういった点で意味があるかもしれないと思えるのかというと、医療機関によってはこの資格取得者に対して資格手当を出しているところがあるからです。
その点に限っては取得する意味はありだと思います。
それがないのであれば取得する意味はないと思います。
診療報酬請求事務能力認定試験とは?
「公益財団法人日本医療保険事務協会が実施している厚生労働省後援の検定試験である。
報酬請求の実務を正しく行うために必要な能力を認定する試験であり実務経験者も多く受験している。
合格率は30%前後を推移しており、医療保険事務資格試験の最難関と言われる。(Wikipedia)」とあります。
厚生労働省後援の資格ということで公的資格と呼ばれてもいますがれっきとした民間資格であります。
ですがこの厚生労働省後援ということと難易度がこれだけ突出して高いということで他の医療事務資格とは一線を画していると見られているようです。
試験概要
受験資格 なし
試験日程 毎年2回 (7月と12月の日曜日または祝日)
試験内容
学科試験 計20問(5者択一式)
実技試験 診療録(カルテ)から手書き方式で診療報酬明細書(レセプト)を作成する試験。
※ 外来から1問と入院から1問の計2問
時間 3時間
受験料 9000円
合格率 30%前後
試験内容と難易度と取得する意味
試験は学科と実技に分かれています。
全て合わせて制限時間が3時間です。
難易度は他の医療事務資格と比較すれば高いです。
ですが世間一般の資格試験のレベルからすると並みといったところでしょう。
逆な言い方をすればその他の医療事務資格が簡単過ぎます。
そして簡単過ぎる医療事務資格は取得したところで何の意味もなく教育講座を持っているスクールや企業に貢いだだけとなります。
ここのところは以前にも書きましたので重複する部分もありますがもう一度言っておきます。
医療事務資格でネット検索しますといろんな企業が資格をとっておいた方がいい、就職、転職に有利、給与に有利などとうたっています。
ですが実情はまったく違います。
そのような資格を持っていたところでなんのアドバンテージもないのです。
完全に単なるキャッチコピーに過ぎないのです。
そこを見極めないと余計なお金と時間を費やすことになってしまいます。
私は純粋に医療事務を学ぶ為としてそのような教育講座などを受講することはいいことだと思います。
独学だとやっぱりきついという人もいるでしょうから。
ただ、就職、転職など仕事に就く場合に持っていれば有利と少しでも思っているのならばそれは違うと言っておきます。
しかし診療報酬請求事務能力認定試験は別格でしょう、という意見には先ほど述べた通りです。
資格手当が出るのならばとる意味はあります。
診療報酬請求事務能力認定試験の内容
この試験は見てもらえれば分かりますが学科と実技があります。
どちらも覚えている知識を競うものではありません。
学科は要するにどれだけ早く診療点数早見表をひけるかということのみです。
解釈の中身を覚えておく必要は一切ありません。
また5者択一式でして5択全ての答えが分からなくても答えは出せます。
例えば、正しい文章はどれという問いに対して
a (1)、(2) b (2)、(3) c (1)、(3)、(4) d (1)~(4)のすべて e (4)のみ
となっていると1つ、2つの正誤が分かれば答えが自動的に分かる場合があるからです。
ですのでここでのポイントは診療点数早見表をいかに体系的に整理して覚えられているかということだけなのです。
それも細かく覚えておかなくてもいいのです。
答えが書いてある箇所をいかに早く見つけるかということだけです。
あと実技ですがこれはレセプトを手書きするので診療報酬請求が理解出来ていないと厳しいです。
ですがこれも点数の出し方、組み立てが分かっていれば出来る筈です。
入院レセプトが難関といいますがこれも過去問を何度もやればパターンとして見えてきます。
そして完璧である必要はなく合格ラインさえ超えればいいのでそこまで難しく考える必要はないと思います。
資格の為の試験
通常の資格試験の場合知識量がそのまま試験の合否に関わってきます。
ですがこの試験の場合知識量は必要とされていません。
覚えていなくても手元の診療点数早見表を見れば答えとされるものはある訳です。
ですので結局スピードとテクニックの問題となります。
どれだけ早くひけるか、どれだけレセプトの手書き問題を解いてきてパターンとして覚えているか。
これはまさしく資格の為の試験なのです。
解き方さえ身につけてしまえば突破出来るのです。
実務との乖離
資格の為の試験である故、実務経験がない学生でも普通に合格出来ます。
ですがだからといって実務が出来るようになるかと言えばそれはまた別問題なのです。
資格試験はあくまで資格試験と割り切っておくことが大切です。
試験に合格したからといって実務レベルが上がるのかというとそんなことはないのです。
手書きレセプトの試験はいらない
なぜかって実務で出てこないからです。
レセコンが入っていない医療機関なんてありません。
手書きレセプトなんてもう出てきません。
実務で出てこないことを勉強して何かメリットってありますか。
もう時間の無駄なんです。
いいえ、手書きレセプトが出来ることはレセプト請求能力の証です、という意見があるかもしれません。
ですが、これを言うと元も子もないかもしれませんが今後一般的に今言われているレセプト請求能力というのは必要なくなっていきます。
いわゆるレセプト点検能力ってやつです。
どういうことかといいますと2022年度にはレセプト全体の9割をコンピューターチェックで完結させるとなっています。
そしてコンピューターチェックルールの公開も行うとしています。
そうなるともう人の目でレセプトを1枚1枚点検する必要がなくなるということなのです。
そしてそうなれば現在医療事務講座で教えていることは一切実務で使わなくなるということになるのです。
そのような遠くない未来がもう見えているのになぜいまだに手書きレセプトの試験を行っているのかは理解出来ません。
まとめ
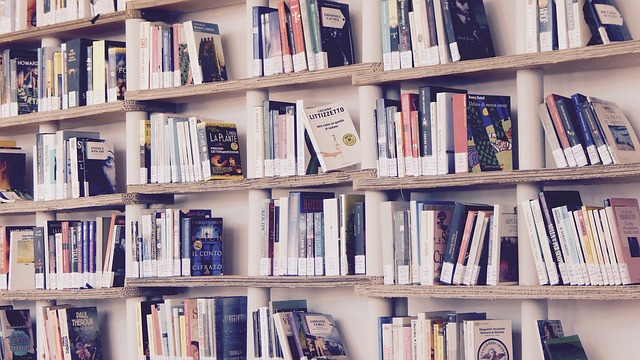
診療報酬請求事務能力認定試験の資格は勤め先の医療機関が評価してくれるのならば取得するメリットはあると思います。
あと純粋に医療事務の理解を深める為の自己研鑽として使うのもいいとは思います。
それ以外の取得することでの過度の期待はしない方がいいと思います。
私が本当に医療事務で働くにおいて必要だと思う資格については過去の記事にまとめています。
 医療事務員が持っていてホントにメリットがある資格とは?【実際は何が有用?】
医療事務員が持っていてホントにメリットがある資格とは?【実際は何が有用?】
あと現場目線で言っておきますと3ヶ月かけて医療事務資格を目指すくらいならPCスキルアップの為の資格を目指した方がよっぽど有意義です。
診療内容に詳しい人よりエクセルをバリバリ使いこなせる人の方が今後の医事課には欲しい人材です。
間違いなく言えることは今後そのようなスキルを持った人の価値が高くなるということです。
今後医事課はスペシャリストよりもゼネラリストを必要とします。
そして最も必要とする人材とは変化について来れる人、いやもっと言うと変化と共に歩める人なのです。
今までの医療事務というイメージは捨てて新しい医療事務像が今後求められてきます。
ぜひ新しい医療事務像に向かって突き進んでくれる人が1人でも多くなってくれればなと思います。
 ごまお
ごまお


