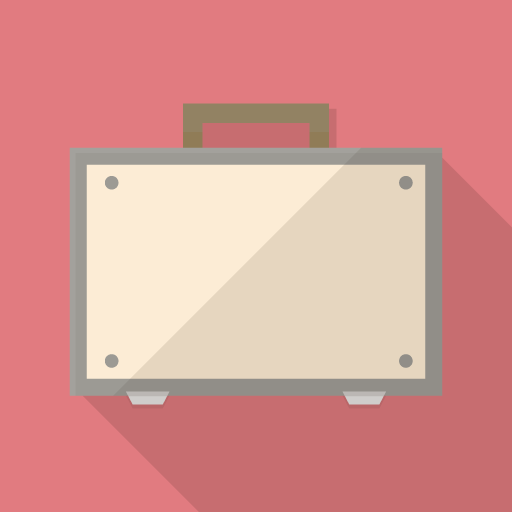医療事務の退職問題については過去に何度も記事にしてきました。
医療事務はブラック、離職率が高い、ストレスでやられるなど一般的にいろんなイメージを持たれています。
といってもこれは本当にイメージ先行です。
ホワイトだと思っている人だっているし、もっと離職率の高い職業だってあるし、ストレスでやられない人もいます。
だからそんな経験談を聞いたり、書き込みを読んだところでそれはあくまでその人個人の感想でしかありません。
ですので「本当につらいのなら辞めればいい」とか「頑張れるところまではやってみれば」というアドバイスもそれはあくまで助言者の主観でしかないのです。
よって相談者と助言者のやりとりというのは、自分の経験にもとづいた話でしかないので実はかみ合っていません。
ということで一度も辞めたいと思ったことのない僕が、今辞めたいと思っている人の気持ちを察してアドバイスをすることは実はできません。
もっともらしいことを言うことはできます。
でもそれだと完全なる偽善です。
そんな言葉はかえって害悪です。
だから今、医療事務を辞めたいと思っている人にかける言葉は残念ながらありません。
ただ客観的に見て、辞めたいと思っている人はこんな傾向であるというところだけ述べておきます。
その傾向とは2つの感覚を失ってしまった、欠けている、というか持てていないよねということです。
逆に言えば、そこが埋まりさえすれば辞めたいとはならないはずだということです。
今まさに医療事務を辞めたいと思っている人こそ読んでみてください。
悩んでいるあなたの何かしらの気づきにはなるはずです。
目次
医療事務を辞めたいと思っている人が失ってしまった2つの感覚

結論
2つとは「貢献感」と「自己効力感」です。
医療事務を辞めたい理由
「せっかく就いた医療事務の仕事だけど、つらくて辞めたい」
そう思いながらもどうすることもできず、そのまま続けているって人は案外多いものです。
そしてそのつらくて辞めたい理由としては次のようなものが挙げられます。
・とにかく忙しい
・覚えることが多い
・職場の人間関係がつらい
・クレーム対応がつらい
・医療現場独特のストレスがつらい
・給料が低い
このようないろんなことが原因で仕事がつらくなり、メンタルを削られていく医療事務員を今まで何人も見てきました。
そしてその人たちには共通点がありました。
それは本来仕事を続けていく上で必要なある感覚が、持てていないということでした。
その感覚とは「貢献感」と「自己効力感」です。
失ってしまった2つの感覚
仕事の究極の目的は、他者貢献と自己成長です。
お金のため、生活のためというのはあくまで副次的要素です。
おそらくなんですが、ある程度お金があって十分生活ができるという状態であっても人は働くんじゃないかと思います。
人はやはり誰かの役に立っている実感が得られてこそ、幸せを感じる生き物だからです。
ですので仕事に貢献感は絶対必要です。
そして働くモチベーションは、自己を承認できていなければ生まれてきません。
その意味では自己効力感も必須です。
この「貢献感」と「自己効力感」は辞めたいと思っている人には間違いなくありません。
ないというか持てていないといった方が正しいです。
ではなぜ持てていないのか?
そこには3つの理由が存在します。
それは
1.人間関係
2.減点主義
3.労働と対価のバランス
です。
順に説明していきます。
貢献感と自己効力感が得られない3つの理由
1.人間関係
人は人である以上、人間関係で悩むことは当たり前の話です。
自分と違う価値観、考え方をする人たちと一緒にいれば、人間関係で何かしらの問題が出てくるのはある意味必然です。
だから仕事のストレスの第1位が人間関係なんてことは、至極当然の話です。
別にそこは注目する点ではありません。
ただ医療事務の場合、他業種とは少し状況が違います。
まず職場が病院だということ。
そして普通だとお客に当たるところが、患者だということ。
そこにはポジティブさなどは生まれない。
むしろネガティブ。
これは良い悪いということではなくて、そういう職場だということ。
だからデフォルト設定がすでにネガティブ寄りなのです。
もうその時点で無意識下に、ストレスはかかっています。
そしてその状況下での患者対応。
そこでかけられる言葉は、ねぎらいや感謝をはるかに上回る問い合わせ、クレーム、ときには暴言。
診察の待ち時間が長いのも、書類が書き上がっていないのも事務員である自分には関係のない話。
でもそのクレームを受けるのは、受付担当である自分。
他の病院スタッフの対応の悪さのクレームを聞くのは、会計担当である自分。
それも込みで仕事なんだよって言ったところで、ほとんどの人は心の奥では納得していません。
これがまず対患者の人間関係です。
あとさらに対上司、対他部署の人間関係もあります。
このように抱える人間関係が非常に多いのが特徴です。
特に対他部署においては、明確な院内ヒエラルキーが存在します。
 病院内ヒエラルキーと医療事務【医事課の役割とポジション】
病院内ヒエラルキーと医療事務【医事課の役割とポジション】
そんなのは気にしなければいいとは思いますが、実際はそんな簡単に処理できる問題ではありません。
このように自分対患者、自分対上司、自分対他部署という中で平気な人は平気ですが、そうでない人にとってはこれ以上の過負荷なストレスはないのです。
このような関係性は、医療事務特有のものです。
これを耐えて乗り越えられる人と、耐えられない人とは完全に2つに分かれます。
2.減点主義
誤解を恐れずに言うと、医療事務という仕事には一切のクリエイティブさは必要ありません。
そんなものは求められていません。
求められているのは精度と正確性。
実施された診療行為を、過不足なく請求しきる知識とスキル。
そこに何かを生み出す創造性は必要ありません。
粛々と間違いなくこなすこと、医療事務にとってはそれが正義です。
ということで、普通に請求できてて当たり前。
だから100点で普通なのです。
これは現場からするととんでもなく高いハードルなのですが、周りは当たり前のようにそう見てきます。
ですので査定されたらマイナス、クレームを受けたらマイナス、他部署から指摘を受けたらマイナスなのです。
そうです、完全なる減点主義です。
基本加点はされず、減点のみ。
だからそうなれば自然と「ミスはダメ」というマインドしか持てなくなります。
何かにチャレンジしようなんて風には決して思いません。
保身に走っても仕方がない状況がそこにはあります。
3.労働と対価のバランス
医療事務の給料は、たしかに安いです。
それももちろん問題ですがもっと本質的な問題は、その給料が働いた分と全然見合っていないと本人が思っているということです。
つまり前述の人間関係や減点主義の影響でかかってくるストレスの大きさに対して、あまりにも給料が少なすぎやしないかって思っているということです。
「こんなにみんなの不満を聞いて、こんなに頑張ってこの給料?」ってことなのです。
給料の額自体はわかって入職してきているはずですが、そこから思っていた仕事のストレス加減が想定を上回っているってことなのです。
そしてまた、医療事務の仕事は想像以上に煩雑で忙しい。
のんびりやってて間に合う仕事なんてない。
つねにマルチタスク、つねに仕事に追われる、それが医療事務です。
だから本人としては、必死で頑張っているつもり。
でもその労働対価としてはあまりに安いんじゃないか、そう感じてしまうってことです。
自己承認
結局上記3つの根本は同じことです。
つまりそれらはすべて自己承認できていない状態なのです。
現状を受け入れられない、自分と向き合えていない状態ともいえます。
そして自己承認できていないからこそ、貢献感も自己効力感もないのです。
だったらどうすればそれらを得ることができるのか?
これは何回も言っていることですが、「挑戦して失敗すること」と「成功体験を得ること」です。
もうそれ以外に自己承認できるようになる方法はありません。
でもこれはさらっと言っていますが、そんなたやすくできることではありません。
まず挑戦した上で失敗してもいいというマインドを持つことがかなり難しい。
先ほども言ったように医療事務は減点主義の職場です。
「絶対失敗したくない」って思うことはあっても「挑戦して失敗しよう」なんてマインドにはまずなりません。
だからそうなるためには、大規模なマインドセット改革が必要です。
そしてそもそもそんなマインドセット改革ができるような人ならば、医療事務を辞めたいとは思わないのです。
ですのでこのアクションプランにはかなり無理があるのも確か。
でも自己承認したいなら、挑戦して失敗して、成功体験を得ないことには自分を認めることなんか一生できません。
まとめ

医療事務を辞めたいと思っている人は辞めればいい、僕にはそうしか言えません。
辞めたいと思っている時点で、医療事務という仕事が好きではないのでしょう。
だったら辞めた方がいい。
好きでもない仕事で成功できるほど人生甘くありません。
でもこれだけは覚えておいてください。
どんな仕事に就こうが、貢献感と自己効力感は絶対必要です。
でないと仕事に楽しさを感じることなんて絶対無理。
仕事に楽しさは必要ですかという質問は愚問すぎるので却下します。
楽しさは必ず必要です。
だって大事な自分の人生の時間の半分くらいはそこにつぎ込むわけです。
それが楽しくないって、そんなのただの拷問です。
そしてそういう状況にしているのは、ほかならぬあなた自身。
だったらその状況を変えることができるのもあなた自身。
貢献感と自己効力感をどうしたら手に入れられるのか、自分なりにしっかり考えてください。
辞めたいと嘆く前にあなたができることは、きっとまだあるはずです。