医療事務の残業については以前にもいくつか記事にしました。
そこでの結論として残業とは、上司の管理能力、個人、部署のマインドセットに大きく左右されるものだということでした。
そして精神論的な話ではなくて具体的にどうすべきかということについて書いてきました。
その中で今回は特にレセプトに的をしぼって残業はいりません、なくせます、という話をします。
「レセプト残業がいらないなんてウソだ」と思っている人こそ、ぜひ聞いてください。
あなたの固定観念をきっと崩してみせましょう。
目次
【医療事務のウソ】レセプト残業なんてホントはいらない!
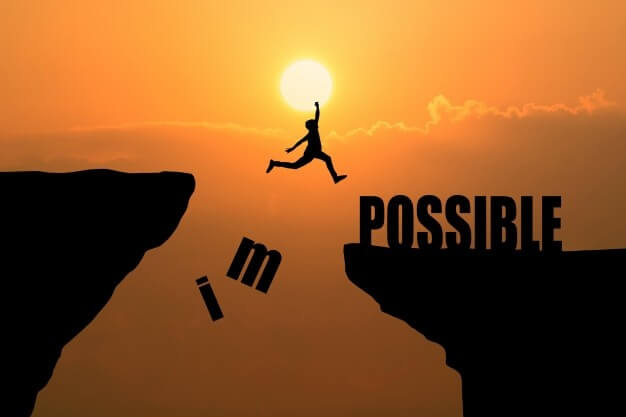
結論
レセプト残業は必要ありません。
必要であるのならばそれはどこかに問題点があり、それを改善できていないということです。
レセプト残業論
医療機関格差
レセプト残業に対するスタンスは医療機関ごとでさまざまです。
「レセプト期間であろうと残業しません」「年末年始は完全に休みです」「休日出勤なんてありえない」という医療機関が存在する一方で、「レセプト期間中の残業は当然あります」というところも数多く存在します。
医療機関によっては曜日に関係なく、毎月1日から10日までは必ず出勤というところもあります。
この部分は一概には評価できません。
その医療機関の医事課の置かれている状況がまったく違うからです。
ですが共通して言えることが1つあります。
それは残業や休日出勤しないとレセプト請求に間に合わないというのならば根本的に何かが足りてないってことです。
足りないのはマンパワー、管理者の能力、担当者の工夫などです。
昔も残業、今も残業
まだ電子カルテもオーダリングシステムもなかった時代、すべてがマンパワー頼りだった昔はそれこそ残業ありきのレセプト業務でした。
僕も23時、24時頃まで残業していたときもありました。
今思えばすごく効率の悪い仕事の仕方だなって思いますが、当時はそれを当たり前と思ってやっていました。
そして今振り返っても当時は残業しないと絶対無理だったよなって思っています。
それぐらい単純に業務量が多すぎて時間が足りませんでした。
しかしそれから月日はだいぶ流れました。
多くの医療機関に電子カルテやオーダリングシステムが入り、レセプト点検に関してはコンピューターチェックソフトがあります。
これが出たことによってある一定数のレセプトの目視点検というものが省けるようになりました。
さらに査定状況を分析しフィードバック、カスタマイズをかけることでより高精度なレセプト作成が可能となりました。
テクノロジーの進歩に感謝なのです。
ですがテクノロジーの格段の進歩に対し、我々医療事務員の仕事への向き合い方はまったく進歩していないようです。
どう大目に見たとしてもICTの進化に伴って業務効率が上がってきているとは到底思えないのです。
確かに昔に比べたら残業は減ってきているのかもしれません。
しかしそもそも現在の時点では減るというよりもなくなっていないとおかしいのです。
レセプト残業対策
医事課の役割、レセプト点検の目的
簡単に言ってしまえば医事課の最大の役割は診療行為をお金に換えること、そしてその利益を最大化させることにあります。
つまりレセプト点検の本来の目的とは何かというと、病院の収益につなげるためのお金の請求となります。
ここをきっちりとおさえておく必要があります。
なぜならこのことに大して気を留めないまま業務に向かっている人が結構な割合でいるからです。
誤解を恐れずにいうと、診療行為を隅々まで拾い上げて正しいレセプトを作成、請求することがプロの仕事ではないのです。
収益となるレセプトを作成、請求することこそがプロの仕事なのです。
大切なのは結果です。
いくら時間をかけて診療行為を余すことなく拾い上げ正しいレセプトを作成したとしても、それがDPC病棟の注射や処置ならば一切コストに反映しません(一部を除く)。
当然その部分の診療行為を入力することは必要です。
EFファイルとして医療資源投下量を正確に入力しておくことは大切です。
ですがそこまでのことです。
それ以上カルテを読み込みこの処置は算定できるだろうかとか、この注射薬の注意事項はどうだっただろうかという確認は何のプラスにもならないのです。
それに時間を使うだけ逆にマイナスなのです。
医療事務では医学の知識、薬学の知識を持っているに越したことはありません。
ですが治療上必要なこととレセプト請求で必要なことは違うのです。
理想は医学的に正しいレセプトでかつ算定のルールにのっとっているレセプトです。
しかしこれを貫こうとすると時間がいくらあっても足りません。
そしてたとえば医学的には正しい病名であってもレセプト上では通らない病名ってたくさんあります。
またエビデンスがある投与方法であっても保険適応されていない使用方法であれば、当然通らないわけでそうなればいわゆるレセプト病名というのをつけてもらわないといけなくなります。
こうなればこれは医学的には正解ではないのです。
しかしレセプト請求としてはそうなって当然なのです。
本来診療行為イコールレセプト内容であることは当然のことです。
ですが診療行為イコールお金になる請求ではないのです。
そこに医療事務員が介在している意味があります。
医療事務員は請求のプロなのです。
どうすれば診療行為を最大限の収益に換えることができるのか、どういう請求が審査機関に引っかからない請求なのか、という点に注力しないといけないのです。
そこの視点がないままでレセプト点検をしていても何の意味もありません。
医療事務員の役割が発揮できていません。
最終地点はどこなのか、達成目標は何なのか、そこを見失ってはいけないのです。
残業の費用対効果
いかに最大限の請求を行えるか。
この視点に立つとレセプトの点検方法から変わってきます。
まず前述の通りカルテを正確に読み、余すことなく拾い上げるということの意味のなさがわかります。
投下した労力に見合う請求点数を拾い上げてこないと生産性なんて上がらないのです。
そして仮に1時間残業して100点分の診療行為を拾い上げてこれたとしてもダメなのです。
なぜならその1時間の人件費は1000円をはるかに超えているのですから。
残業分を上回る売り上げを上げてこそ残業する意味があります。
さすがに限られたレセ期間で業務を遂行しないといけないのですから、そこまでを求めるのも酷な話ですが根底には持っておくべき思考なのです。
フォーカスするところ
請求の最大化をするに当たってどこに着目するかということが重要です。
そして当然、診療報酬のルールにのっているというのは大前提です。
それプラスもう1つフォーカスするところがあります。
それは審査機関です。
そんなことは担当者 の人はわかっていることでしょう。
ですがここで何を言わんとしているのかというと、「診療報酬のルールにのっとった正しい請求イコール査定のない請求ではない」ということです。
つまり最重要視すべきは審査機関ということです。
そもそも審査機関は全国に支部がありそれぞれがローカルルールを持っています。
そしてまた審査のトレンドというものがありその時流を読む力が必要です。
だから参考書を読んで問題を解くというスタイルでは効率が悪いのです。
まず答えを見てから問題を解いていくべきなのです。
ここで言う答えとはすなわち査定結果です。
現在の自院の請求ではどこに注目されていて査定されやすくなっているのか、どういうレセプトが通りやすく、また通りにくいのか?
そこの部分をまず徹底的に分析することが先決です。
そこをしないまま漠然と時間を投下し、レセプト作成をしても請求を最大化することは難しいです。
多くのレセプト残業を行っているところはこの部分の罠にはまっています。
逆算から入らないからいくら時間があっても足りないのです。
初めに答えからの分析とそれによる点検のゴール地点を決めておけば時間の線引きはできるのです。
大切なのはゴール地点を決めるということです。
それがないとパーキンソンの法則にまんまとはまってしまうのです。
 医事課の生産性とは? 【パーキンソンの法則】
医事課の生産性とは? 【パーキンソンの法則】
完璧はない
以前に仕事の完璧さについて記事にしました。
 完璧を目指すよりまず終わらせろ【医事課の仕事は完了主義】
完璧を目指すよりまず終わらせろ【医事課の仕事は完了主義】
完璧なレセプトなんてありません。
そして、完璧かどうかを判断するのはあなたではありません。
それは審査委員の役目です。
だったらいくら時間をかけたところでそれは終わりがないのです。
だから必要なのは決断力と諦めることです。
ここまでしたからもう終わり。
それでいいのです。
そうしないと残業をなくすことなど絶対不可能です。
何か困ることある?
上記の完璧主義の話にも関係しますが、たとえ残業をなくした結果、査定率が上がってしまったという事態になって何か困りますか?
責任をとらされますか?
そんなことありません。
いやいやその発言はあまりにも無責任すぎるだろうっていう人もいると思います。
ですがそれなら反対に聞きますが、その上がった査定率は残業すれば必ず下げることができるのですか?
そんなことは誰にもわかりません。
そこには決まった正解なんてないのです。
だったら残業の意味って何なの?ってことです。
結局つきつめると残業って究極の自己満足なんです。
自分は頑張ったと思いたい、そのためだけに残っているようなものです。
いや違う、業務量が多すぎてどうやっても残業しないと回らないっていう人もいるかもしれません。
ですがそれも同じこと。
業務量が多すぎるのであれば残業するよりまずすべきは上司との交渉です。
自分の能力の問題ではない、作業量の問題なんだということを主張しないといけません。
それはもうやっていて、それでもその状態なのであれば考えられることは2つです。
自分自身に甘いのか上司が無能かのどちらかです。
これはどちらも残念な状態ですが、どういう方向であれ次の場面には進んでいけます。
ですがそれもしないでレセプト業務だから仕方がない、残業は当然出てしまうと、いう考えでは残業がなくなる日は来ません。
朝15分かかる仕事は昼には30分かかり夜には2時間かかると言われています。
この道理でいくと夜2時間かけたレセプト点検は朝なら15分で終わるということになります。
さすがにそこまでは言い過ぎかもしれませんが半分ぐらいにはできるはずです。
そう考えると日中のタイムスケジュールの立て方で、いくらでも残業回避の方法は見つかるはずです。
残業が回避できないのはできないのではなくて、自分でしようとしていないからなのです。
まとめ

レセプト残業はなくせます。
これは本当です。
なくせないのは個人の問題か組織の問題かその両方かです。
組織のトップが残業もやむなし派ならば残念ながらなくなることは永遠にありません。
残念ですが諦めて下さい。
まだまだ医療機関では残業が頑張っている証、いいこと、と見る風潮が強いように思います。
僕は真っ向否定派です。
残業は無能、定時上がりは有能と見ます。
ですがこれって誰でもやろうと思えばできることなんです。
やろうと思わないだけなんです。
できると思っていないだけなんです。
仕事は結果を出してナンボです。
仕事量とは「集中力 × 時間」で生み出されるものです。
仕事とは日々改善を重ねていき自己成長させていくものです。
それに対して残業ってプラスになる要素なんて何もないのです。
ましてレセプトを残業して仕上げることにどれだけのメリットがあるのでしょうか。
ですがここで僕がいくら語ろうとも、実際現場で毎月残業している人から見れば「理想論ばかり言ってんじゃねえよ」って思うことでしょう。
僕も昔はそう思っていました。
毎月レセ期間は深夜近くまで残業していた頃、研修会で一緒だったとある医療機関の医事課の人が「うちは残業はない。やろうとしないからできないんだよ」という主旨のことを言っていました。
まさに今回の僕の言っているようなことです。
そのときはこう思っていました。
「あなたのところではそうできるのでしょう。しかしうちではできるはずがない」と。
結局最初の決めつけ、バイアスがすべてをダメにするのです。
一歩も踏み出していないのに結論を出すことが間違っているのです。
当然一気に残業が減っていくなんてことはありません。
そこには日々の積み重ね、改善の足跡が刻まれていって初めて成果として現れるのです。
まず来月の残業時間は今月のマイナス1時間を目標にする。
そこからです。
そのためには何を変えていくか。
順番かやり方かほかの何かか。
そして何をアップデートしていくのか。
診療報酬の知識か、医学の知識か、薬の知識か、査定のトレンドか。
考えることはいろいろあります。
そしてこの考える行為が大切であり必要なのです。
思考停止して毎月ルーチンワークとしてレセプト点検していてもそれなりに仕事は回ります。
ですがそれでは仕事で最も大切な自己成長が伴わないのです。
レセ期間に定時に帰れておまけに自己成長もできる、それができるようになれば毎日の仕事がもっと楽しくなっていくはずです。
そんな自分像に一歩でも近づいてみませんか?
1ミリでも行動すればきっと何かが変わり始めます。
ぜひ行動しましょう。


